


vol.15
スポーツ文化評論家 玉木 正之(たまき まさゆき)

プロフィール
1952年京都市生。東京大学教養学部中退。在籍中よりスポーツ、音楽、演劇、 映画に関する評論執筆活動を開始。小説も発表。『京都祇園遁走曲』はNHKでドラマ化。静岡文化芸術大学、石巻専修大学、日本福祉大学で客員教授、神奈川大学、立教大学大学院、筑波大学大学院で非常勤講師を務める。主著は『スポーツとは何か』『ベートーヴェンの交響曲』『マーラーの交響曲』(講談社現代新書)『彼らの奇蹟-傑作スポーツ・アンソロジー』『9回裏2死満塁-素晴らしき日本野球』(新潮文庫)など。2018年9月に最新刊R・ホワイティング著『ふたつのオリンピック』(KADOKAWA)を翻訳出版。TBS『ひるおび!』テレビ朝日『ワイドスクランブル』BSフジ『プライム・ニュース』フジテレビ『グッディ!』NHK『ニュース深読み』など数多くのテレビ・ラジオの番組でコメンテイターも務めるほか、毎週月曜午後5-6時ネットTV『ニューズ・オプエド』のMCを務める。2020年2月末に最新刊『今こそ「スポーツとは何か?」を考えてみよう!』(春陽堂)を出版。
公式ホームページは『Camerata de Tamaki(カメラータ・ディ・タマキ)』
大坂なおみ選手の「鬱病」は、
現代の一流アスリートの慢性病?
原因は、選手を 「ロボット化」する
「ビッグデータ・スポーツ」か?
6月初旬、東京オリンピックの開会式(7月24日)まで50日を切ったが、新型コロナの感染は収束する気配を見せず、「中止」や「延期」を主張する声も収まらないなか、スポーツ界に、また別の注目すべき「大事件」が起きた。
テニスの大坂なおみ選手が全仏オープンを棄権し、自分が「鬱病」に悩み続けていた事実を告白したのだ。これは東京オリンピックが無事開催できるかどうか、という問題と肩を並べるほどの「大事件」だ。というのはコロナ禍での東京五輪開催(または中止)が、将来の「オリンピックの形」に影響を与えるのと同様、大坂選手の「告白」も将来の「スポーツの姿」に大きな影響を与えると思えるからだ。
五輪大会については、現在のように過度に肥大化した大会を将来も続けて良いものか…という疑問が今後必ず浮上してくるだろう。その結果どのような「改革案」が具体化するのか―IOC(国際オリンピック委員会)を国連管理下に置き、スポンサーやテレビの放映権料で支えられている運営をIOC加盟国のGDPによる分担金で運営する……とか、オリンピック発祥の地であるアテネでの常時開催……など、様々な案が出てくるかもしれない。
今回はその話題には深入りしないが、大坂なおみ選手の「鬱病」については、けっして彼女ひとりの問題ではなく、多くの一流アスリートたちが抱えている共通の大問題として捉える必要があるだろう。
現在、世界のトップ・アスリートたちは、誰もが強烈なプレッシャーのなかでプレイすることを強いられ、多くの選手が何らかの精神疾患を抱えているという調査報告もある。
FCバルセロナで活躍したサッカー選手で世界的に人気が高く、2010年のワールドカップでスペインを初優勝に導き、MVPに選ばれたアンドレス・イニエスタ選手も、自ら鬱病を経験したことを告白している。
ヨーロッパの一流クラブでプレイしているサッカー選手の40%近くが何らかの精神障害を抱えているとの調査結果もあり、イニエスタ選手がJリーグのヴィッセル神戸に移籍したのも、厳しい欧州サッカーの戦いやメディアの論調から逃れるためだったとも言われている。
またアテネ、北京、ロンドン、リオの五輪4大会の競泳で23個の金メダルを獲得したマイケル・フェルプス選手も(離婚した父親との不仲という家庭の事情もあり)鬱病や神経症と闘うなかで競技に臨んでいたという。
小生の取材経験のなかでも、現役時代のボクサー具志堅用高選手は、常に必死になって恐怖と闘うなかでリングに上がり、世界王者になったあとのほうが恐怖感が強くなったと語っていた。また現役プロ野球選手時代の山本浩二選手や掛布雅之選手は、毎年ペナントレースの開幕が近づくと、今シーズンは1本もヒットやホームランを打てないのではないかという恐怖から、夜眠れなくなったと語っていた。そういう選手は神経がナイーヴすぎるというのではなく、多くの選手が同じような話をしてくれたのだった。
世界ランクの1位にまで上り詰めた大坂なおみ選手も、ランキングから落ちる恐怖や、試合に敗戦する恐怖などもプレッシャーとなり、さらに本人自身が「内向的」という性格で、一流選手に出席が義務化されている試合後の記者会見も、多大な精神的プレッシャーとなり、自ら一時的にコートを離れるという選択を決意をしたと考えられる。
大坂なおみ選手は2018年8月全米オープンに初優勝したころから鬱病に悩まされ始めたと告白したが、そのときの記者会見で興味深い回答を口にしていた。記者が「テニスをやっている子供たちにメッセージを……」と言うと、彼女は「テニスを楽しんで……そして、私を目指さないで……」と答えたのだ。
そのときは、自分を倒すような強い選手にならないで……とジョークを言ったと誰もが思ったが、彼女が鬱病をカミングアウトしたあとでは、別の深い意味があったとわかる。彼女は、私の経験しているような苦しいテニス(スポーツ)はやらないほうがイイ……と子供たちに忠告したのだ。
現在最先端の超一流のテニス選手の闘いはまず「データとの熾烈な情報戦」を勝ち抜くこととも言われている。あの選手のあの位置にボールを打つと、この位置に返される……あの選手へのサーヴ(リターン)はどこに打てば(返せば)良いか……といったことが全て"ビッグデータ"によって導かれ、その分析結果を頭に入れたうえで、コート上での闘いが展開されるのだ。
もちろん選手の判断力や技量や身体能力も重要だが、それらを活用する基になる情報は欠かせない。他のスポーツも同じで、最近のメジャー野球では打席に立った打者によって一二塁間に3人の内野手が守ったり、投手が投球の合間にポケットからメモを取り出し、打者の情報を確認したり……バレーボールの監督が、試合中iPadを片時も手放すことなく選手に指示を送る。それらは、現代の「進化したビッグデータ・スポーツ」の姿と言える。
それに対して一流のアスリートたちが、自分のやっていることに疑問を抱くのは当然だろう。自分はデータ通りに動く「ロボット」に過ぎないのではないだろうか……?
メジャーリーグ・エンジェルスの大谷翔平選手の二刀流―いや、一流投手でホームラン打者で盗塁まで決める「三刀流」は、「ロボット化(?)」を余儀なくされた現代の「ビッグデータ・スポーツ」に対する「野球を楽しむ選手」の反抗と言えるかもしれない。が、誰もが大谷選手になれるわけではない。
メジャーでは"ビッグデータ・ベースボール"の行き過ぎを是正するため、内野手は一二塁間と二三塁間に2人ずつ配置しなければならないということをルール化する実験を、近くマイナーリーグで試し始めるという。
大坂なおみ選手がコートに戻ってくる姿を早く見たいと思うのは誰もが願うところだが、「非人間的な闘い」にまで「進化」した「ビッグデータ・スポーツ(テニス)」を「人間的な姿」に戻す方法も改めて考える必要がありそうだ。
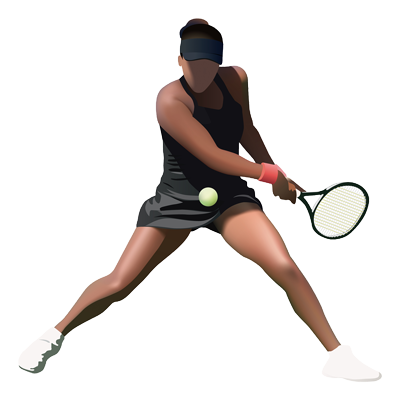




(Up&Coming '21 盛夏号掲載)




