


vol.17
スポーツ文化評論家 玉木 正之(たまき まさゆき)

プロフィール
1952年京都市生。東京大学教養学部中退。在籍中よりスポーツ、音楽、演劇、 映画に関する評論執筆活動を開始。小説も発表。『京都祇園遁走曲』はNHKでドラマ化。静岡文化芸術大学、石巻専修大学、日本福祉大学で客員教授、神奈川大学、立教大学大学院、筑波大学大学院で非常勤講師を務める。主著は『スポーツとは何か』『ベートーヴェンの交響曲』『マーラーの交響曲』(講談社現代新書)『彼らの奇蹟-傑作スポーツ・アンソロジー』『9回裏2死満塁-素晴らしき日本野球』(新潮文庫)など。2018年9月に最新刊R・ホワイティング著『ふたつのオリンピック』(KADOKAWA)を翻訳出版。TBS『ひるおび!』テレビ朝日『ワイドスクランブル』BSフジ『プライム・ニュース』フジテレビ『グッディ!』NHK『ニュース深読み』など数多くのテレビ・ラジオの番組でコメンテイターも務めるほか、毎週月曜午後5-6時ネットTV『ニューズ・オプエド』のMCを務める。2020年2月末に最新刊『今こそ「スポーツとは何か?」を考えてみよう!』(春陽堂)を出版。
公式ホームページは『Camerata de Tamaki(カメラータ・ディ・タマキ)』
ロシアは「オリンピック休戦」期間中にウクライナへ軍事侵攻。
IOCやメディアは、石原慎太郎氏も賛成した「五輪の脱ナショナリズム」を実行するべきではないだろうか!?
コロナ禍の下でのオリンピック東京大会に続いて北京冬季大会が閉幕した。と思ったら、ロシアがパラリンピック冬季大会の開幕前に、ウクライナへの軍事侵攻を開始した。
1994年ノルウェーのリレハンメル冬季大会以降、オリンピックの年には国連総会で常に「オリンピック休戦」が決議されている。「休戦」の期間はオリンピック開幕の7日前からパラリンピック閉幕の7日後までとされ、今回の北京大会でも同様の期間で提案され、ロシアも含む満場一致で決議された。そこでIOC(国際オリンピック委員会)とIPC(国際パラリンピック委員会)は、ロシアの「五輪休戦協定違反」を非難する声明を発表した。
とはいえ、IOCの側にも少々首を傾げたくなる事情が存在しているのだ。それは、競技の種目数が大会ごとに増加していることだ。
競技種目数の増加だけなら、オリンピック肥大化の問題にはなっても、「休戦協定」とは無関係と言える。が、増加した種目の種類の性質が少々問題なのだ。
今回の北京冬季五輪ではスキー・ジャンプ混合団体、スノーボード・クロス混合団体、フリースタイル・スキー・エアリアル混合団体の3種目が新種目として追加された。
ここで注意したいのは、団体種目(団体競技、団体スポーツ)は、チームプレイとはまったく異なるスポーツだということである。
チームプレイはチームの何人かが同時に競技の場に現れ、互いに影響を及ぼし合って相手チームと闘うスポーツのことで、冬季五輪では、カーリングやスケートのパシュート、それにアイスホッケーなど、夏季五輪ではサッカー、バスケットボールなどの球技や、バトンのパスワークが伴う陸上競技のリレーなどがチームプレイと言える。
一方、団体スポーツは、一人ひとりの選手が個人競技と同様の試技を別々に行い、その成績(タイムや距離)を足し算した合計の成績で争う競技で、北京で新種目となったものやフィギュアスケートの団体はすべてチームプレイではなく団体種目。夏季五輪では体操団体や卓球団体などが、団体種目と言える。
団体種目の場合も選手同士が励まし合ったり応援し合ったりして一つのチームとしてまとまるため、チームプレイと混同される場合が少なくない。とりわけ日本の体育教育では体育祭の入場行進や組体操のように揃って行う行為が多く、運動部の合宿でも全員揃っての散歩やランニングもあり、団体行動がチームプレイと混同されるケースも少なくない。
が、そもそもチームプレイとは各選手が異なる動きを行うことによって一つのチームになることで、団体行動や団体種目は各選手が同じ(ような)動きをすることでまとまること(スポーツ)と言える。
そこで、オリンピックで団体種目が増えたことだが、IOCは「男女平等」を推進する種目として男女混合団体の種目を増やしているようだ。が、「男女平等」なら別に「混合団体」にしなくても男女に同じ種目を取り入れればそれでいいはずで、特に「混合団体」にする必要はないはずだ。しかも「団体」にすると、アスリート個人のスポーツの技術の優劣や見事さよりも、日本が勝った……中国が勝った……と、どの国が勝ったかという結果ばかりに興味が移ってしまう可能性が高くなる。
オリンピックの憲法と言える「オリンピック憲章」の第1条には、オリンピックは《選手間の競争であり国家間の競争ではない》と明記されている。が、団体戦が増やされていると言うことは、IOCが《国家間の競争》に目が向くよう仕向けているとも言える。
確かに《国家間の競争》とするほうが、スポーツの技術やルールなどを知らなくても見物人の(自国を応援する)興奮の度合いが増して、大会も盛りあがるかもしれない。が、オリンピック憲章は《オリンピック競技大会では各NOC(国内オリンピック委員会)によって選ばれ、IOCが参加を認めた選手たちが一堂に会する》と続けられている。
ということは五輪憲章の理念に則れば、東京大会や北京冬季大会に過去のドーピング違反から国名を名乗れずROC(ロシアオリンピック委員会)という名称で参加したロシアのように、日本はJOC(日本オリンピック委員会)、アメリカはUSOPC(アメリカ・オリンピック・パラリンピック委員会)と呼ばれて参加するほうが正しいと言える。
しかし実際には、IOC自身が各NOCの名称ではなく国名の使用を認め、国旗と国歌の使用も認め、そして「国別対抗戦」としか思えない団体戦を増やし、さらに「国別メダル獲得数」も、東京大会や北京大会の組織委員会のホームページに掲載するようになった。つまり「国家間の競争ではない」はずのオリンピックで、IOC自身が憲章に違反して「国家間の競争(ナショナリズム)」を煽り、五輪大会を(感情的に!)盛りあげているとしか思えないのだ。
1964年の東京五輪の頃は当時のブランデージIOC会長を初め、優勝者のための国歌吹奏や国旗掲揚をやめようという意見もあった。そして東京大会に接した石原慎太郎氏も、その意見に賛成した。《私は以前、日本人に希薄な民族意識、祖国意識を取り戻すのにオリンピックは良き機会であるというようなことを書いたが、誤りだったと自戒している。民族意識も結構ではあるが、その以前にもっと大切なもの、すなわち、真の感動、人間的感動というものをオリンピックを通じて人々が知り直すことが希ましい》(1964年10月11日読売新聞/講談社編『文学者の見た世紀の祭典東京オリンピック』講談社文芸文庫より)
国家意識を刺激している現在のオリンピックとIOCの姿勢が、ロシアのウクライナ軍事侵攻に繋がった……と言うのではないが、半世紀前に文学者が認めた「五輪の脱ナショナリズム」を、今こそIOCも、そしてメディアも思い返すべきではないだろうか。

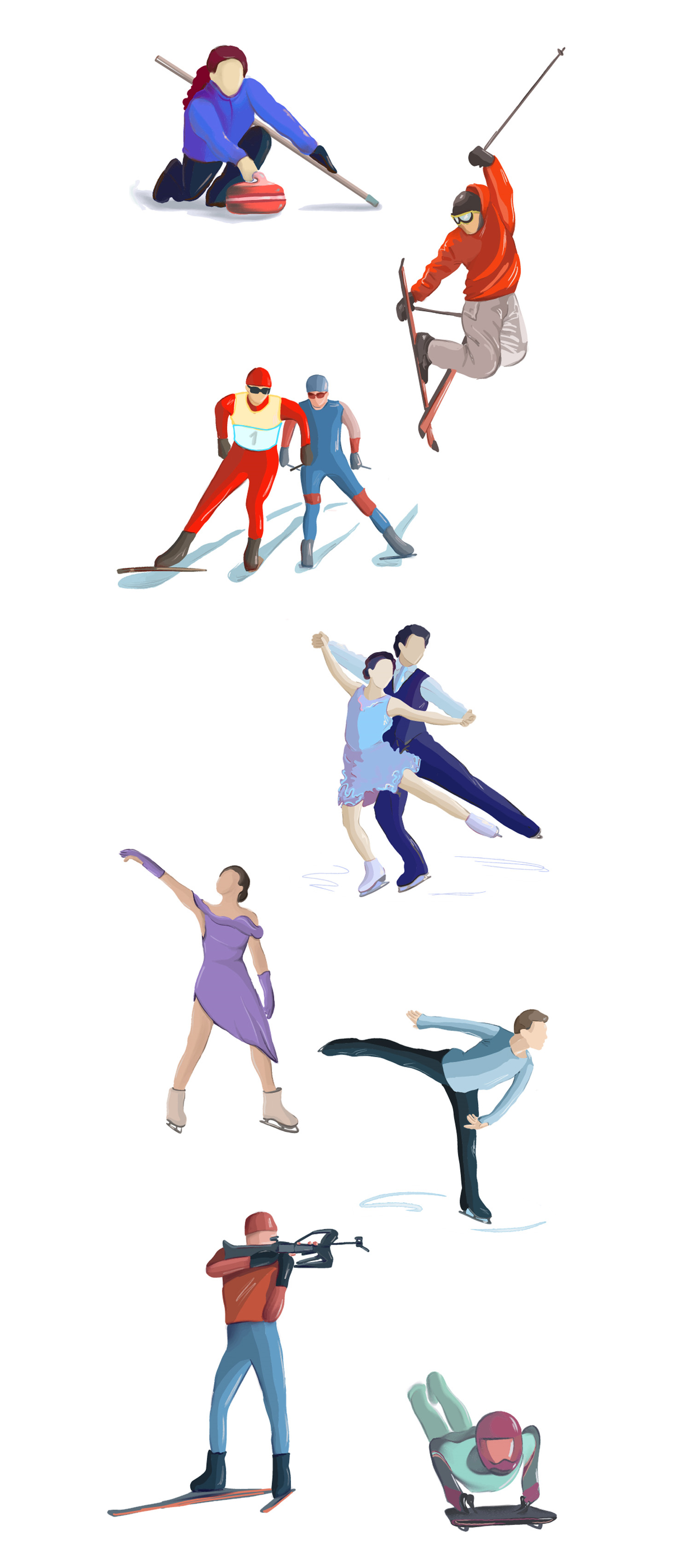
(Up&Coming '22 春の号掲載)





