|
|
|
組杭構造に対する面外方向の設計は、「各杭の荷重分担を考えて杭を1本ずつ設計する方法」と、「組杭構造のまま全体の面外解析をして設計する方法」があります。面外方向の設計にあたって、各杭の荷重分担を考えるということは、杭を1本ずつバラして設計を行うことが前提です。荷重分担率を使って各杭の作用荷重を決定し、各杭毎に単杭の面内解析を行い設計してください。
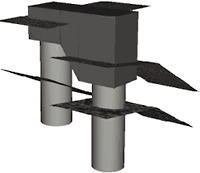 |
| ▲荷重分担率を考慮すべき単列深礎の例 |
なお、本ソフトでは、組杭構造のまま面外解析を行うこともできるので、下記【1】〜【3】のいずれかの方法で設計してください。
【1】基礎が回転変形を生じない場合の計算方法
| 1. |
設計手順のポイントは、面外方向の荷重に対して、杭を1本ずつバラして面内解析を実行することです。このとき各杭に作用する荷重は、荷重分担率を使って算定します。荷重分担率は、面外解析を用いた予備計算を行って求めてください。 |
| 2. |
予備計算の方法面外解析の弾性解析時において、各杭頭に支点を設け、δ1=δ3の支点強制変位(1mm)を与え、計算を実行します。(具体的には、製品HELP
Q1-11を参照して下さい。) |
| 3. |
荷重分担率を使って各杭の作用荷重を算定し、各杭毎に単杭状態の面内解析を実行してください。 |
【2】基礎が回転変形を生じる場合の計算方法
| 1. |
設計手順のポイントは、【1】と同様で、面外方向の荷重に対して、杭を1本ずつバラして面内解析を実行することです。このとき各杭に作用する荷重は、荷重分担率を使って算定します。荷重分担率は、面外解析を用いた予備計算を行って求めてください。 |
| 2. |
予備計算の方法面外解析の弾性解析時において、フーチング中心に集中荷重P2(100kN)を作用させ、計算を実行します。(具体的には、製品HELP
Q1-11を参照して下さい。) |
| 3. |
荷重分担率を使って各杭の作用荷重を算定し、各杭ごとに単杭状態の面内解析を実行してください。 |
【3】組杭のまま設計を行う場合の計算方法
設計手順のポイントは、面外方向の荷重に対して、組杭のまま全体の面外解析を実行することです。本プログラムは自動的に杭組状態のまま面外解析を実行しますので、荷重分担率を求める予備計算は不要です。
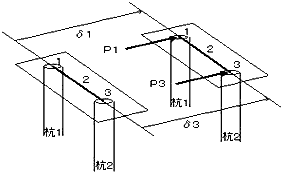 |
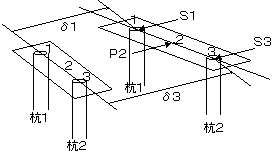 |
| ▲回転変形なし |
▲回転変形あり |
|
Page Top 
|
| SUPPORT TOPICS |
VRのなぜ? 解決フォーラム |
保守・サポートサービス関連情報 |
| UC-win/Road |
|
|
UC-win/Road上での地形編集では、地形パッチを作成することで任意の地形を編集することが可能です。データ作成を続ける中で、初期の地形パッチ範囲では不足のため、範囲を広げたい場合や、隣り合う地形パッチを一つの地形パッチとして扱いたい場合、そのままでは不可能です。このような場合、作成済の地形パッチを一旦削除し、新たに範囲を選択する事になりますが、地形を相当編集しているような場合、再度設定することが困難です。編集・選択した地形パッチの情報を生かして、合成を行うには、次の手順で行ないます。
- それぞれの地形パッチを保存します。
- メモ帳などで、それぞれのファイルを開きます。
- 片方の内容をもう一方にコピーします。この時、ヘッダー及びフッターは不要ですので、座標の行だけをコピーします。
- 新しいファイル名で保存します。拡張子はxmlとします。
- Road上の元の地形パッチを削除します。
- 新しい地形ファイルを読み込みます。
|
 |
このように、地形パッチファイルを合成することで、Road上で行えなかった範囲変更が可能になります。
地形パッチのポイント数が2000個を超えた場合、3次元空間上での編集を行うことができません。地形パッチの編集画面内では、2000個の制限を無視することで編集が可能となります。合成を行ったり範囲を広げたような場合、制限を超えるケースがありますのでご注意ください。
またDMデータや、DXFファイルから地形情報を読み込んだような場合は、10万を超えるようなポイントで構成されるケースがありますが、標高点が多くなるほど、切り盛りの計算が多くなり、道路生成の処理時間がかかります。遠景は、Road標準搭載の50mメッシュをそのまま利用いただき、道路周辺は地形情報を読み込んで、測量点を利用する事をお勧めします。またポイント数は、適度な間隔のものを使用されることをお勧めします。
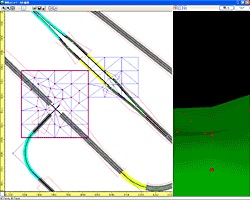 |
|
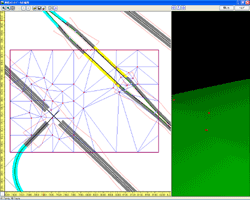 |
| ▲合成前 |
|
▲合成後 |
|
Page Top 
|
|
|
 非線形要素の特性について(1) 非線形要素の特性について(1)  非線形要素の特性について(2) 非線形要素の特性について(2)
|
今回は、軸力変動が生じるモデルについてご説明いたします。
UC-win/FRAME(3D)がサポートしている非線形梁要素は「ファイバー要素」と「M-φ要素」があります。このうち、ファイバー要素は軸応力と軸ひずみの関係において非線形特性を考慮したものであり、自動的に軸力変動を考慮することができます。これに対して、M-φ要素は軸力変動を考慮することができません。例えば、死荷重時の軸力を用いてM-φ特性を算出し解析を行う要素です。軸力変動が生じるモデルに対して、これらの要素を用いたとき、結果にどのような違いが出るのか検証します。
検証するモデルは、下図のようなラーメン構造物のプッシュオーバー解析を行います。
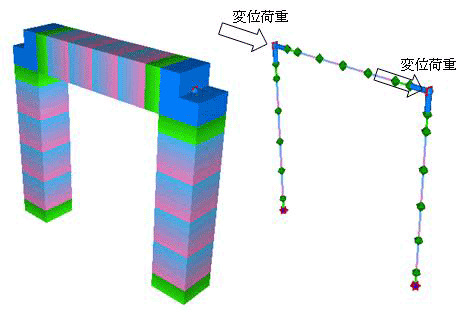 |
| ▲図1. モデル概要 |
両者の荷重変位曲線(P-δ曲線)を以下に示します。上がファイバー要素を用いた結果であり、下がM-φ要素を用いた結果です。
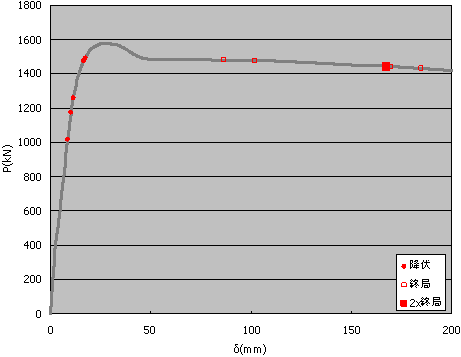 |
ファイバー要素を用いた結果
|
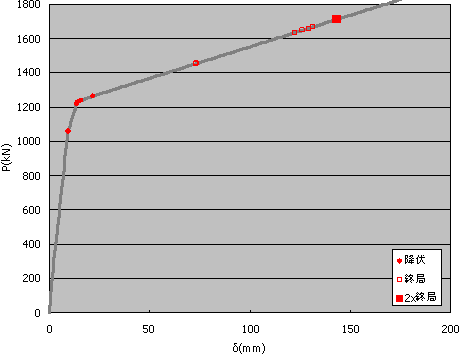 |
M-φ要素を用いた結果
▲図2. 荷重変位曲線 |
ファイバー要素では全ての塑性ヒンジが終局に達するより1要素の曲率が終局曲率の2倍となる方が早く、これにより終局耐力が決定しています。これに対して、M-φ要素では全ての塑性ヒンジが終局曲率に達する方が早く、これにより終局耐力が決定することになります。初降伏までは大きな差は見受けられませんが、終局時には耐力および変位に大きな差が見られます。これらを元に算出した許容塑性率にも1.5倍程度の差が生じており、軸力変動モデルに対するM-φ要素の適用には注意が必要です。
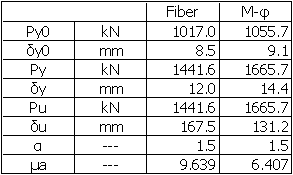
▲表1. 結果一覧 |
以上、3回に分けてお送りして参りましたが、要素の特性をご理解頂いた上でご活用下さい。
 非線形要素の特性について(1) 非線形要素の特性について(1)  非線形要素の特性について(2) 非線形要素の特性について(2)
|
|








