| Q1. |
配力筋の加工図を「D13*10860」ではなく、「D13*8000」と「D13*2860」に分けたいが?
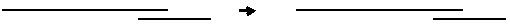 |
| (G51)D13*10860 |
(G51)D13*8000 (G52)D13*2860 |
|
| A1. |
入力画面の「基本情報」->「生成条件」->「縮尺・他]の「配力筋記号付け」の選択を「記号1つ」から「記号複数」に変更する事で、上図のように作図する事ができます。
(但し、一部の配力筋のみでなく、すべての配力筋が上図のように変更されます。) |
| |
|
| Q2. |
設計計算プログラムから連動した場合、コンクリート等の数量及び数量計算の出力は出来るか? |
| A2. |
UC-CAD擁壁配筋図の「生成条件」->「生成条件3」の「数量計算」を「計算する」に設定し生成実行後、「ファイル」->「上書き保存」または「名前を付けて保存」で生成データを保存したタイミングで、数量計算データファイル「***(数量).TXT」を作成します。
このデータをテキストエディタ(windows付属のメモ帳やワードパッドでも可)で開いてご利用ください。
( *** は、「保存したファイル名称」です。 ) |
| |
|
| Q3. |
L型擁壁の平面折れは何度まで対応可能か? |
| A3. |
擁壁前面の折れ角を図のθとした時、85度から-85度までの折れの作画に対応可能です。
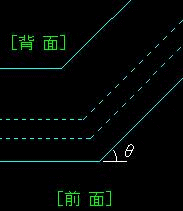
なお、逆T型擁壁も同様です。
現版では、平面形状で折れ有りの設定とする場合には
「正面形状 一定勾配 竪壁天端形状、開口部 なし、 底版付属物なしの条件に自動でセットします。」
その為、これらに該当する形状には対応出来ませんので別途、UC-Drawにて加筆修正を御願いいたします。 |
| |
|
| Q4. |
鉄筋の定尺を変更したいがどうすれば良いのか? |
| A4. |
鉄筋の最大長さを変更したい場合には、
オプション→作図設定→④材料基準値の鉄筋最大長
を変更いただき利用下さい。 |
| |
|
| Q5. |
土木構造物設計ガイドラインに従った作図(定尺鉄筋対応鉄筋長:50cmピッチ)はどのようにするか?
|
| A5. |
以下の設定により生成が可能となります。
<簡易入力で作成する場合>
・「基本情報」->「生成条件」->「生成条件3」の生成条件画面の「定尺鉄筋」指定を「使用する」に設定。
( 配力筋の定尺鉄筋の作図方法には、「変化筋なし」、「変化筋あり」の2つの方法が有ります。その内容は、ヘルプの「目次」->「処理の考え方」->「定尺鉄筋の扱い」を参照してください。 )
・「オプション」->「鉄筋基準値」の鉄筋基準値画面の値を土木構造物設計ガイドラインにあわせる。
( 主鉄筋の詳細入力情報生成時にたて壁主鉄筋長を定尺とするために使用します。 )
・「オプション」->「作図設定」の作図設定情報変更画面の「材料基準値」を土木構造物設計ガイドラインにあわせる。
( 生成の際にたて壁主鉄筋と配力筋を定尺とするために使用します。 )
・「基本情報」、「形状情報」、「鉄筋情報」->「簡易入力」の情報を入力し「図面生成」->「生成実行」を行う。
※但し、たて壁主鉄筋については以下の条件の場合に定尺鉄筋となります。
1)たて壁断面の前背面にテーパーが無い場合。
2)たて壁断面の前背面にテーパーが有り、「基本情報」->「生成条件」->「生成条件1」の「たて壁主鉄筋の形状」が「鉛直」の場合。
たて壁断面の前背面にテーパーが有り、たて壁主鉄筋を鉛直としない場合は、「簡易入力」後に「詳細入力」でたて壁主鉄筋を定尺鉄筋に調整し「生成実行」を行ってください。
<詳細入力で作成する場合>
・「基本情報」->「生成条件」->「生成条件3」の生成条件画面の「定尺鉄筋」指定を「使用する」に設定。
( 配力筋の定尺鉄筋の作図方法には、「変化筋なし」、「変化筋あり」の2つの方法が有ります。その内容は、ヘルプの「目次」->「処理の考え方」->「定尺鉄筋の扱い」を参照してください。 )
・「オプション」->「作図設定」の作図設定情報変更画面の「材料基準値」を土木構造物
設計ガイドラインにあわせる。
( 生成の際にたて壁主鉄筋と配力筋を定尺とするために使用します。 )
・「基本情報」、「形状情報」、「鉄筋情報」->「詳細入力」の情報を入力し「図面生成」->「生成実行」を行う。 |
| |
|
| Q6. |
平面折れ形状での配力筋の継ぎ手作画は可能か? |
| A6. |
平面折れ擁壁の配力筋の継ぎ手作図はサポートしておりません。
平面折れ擁壁で配力筋に継ぎ手を作図される場合は、お手数ですが、生成実行後、UC-Drawにて編集して頂く必要が御座います。 |
| |
|
| Q7. |
重ね継手長の設定はどのようにするのか? |
| A7. |
重ね継手長の設定は、「オプション」→「鉄筋基準値」と「オプション」→「作図設定」→「材料基準値」の2ヶ所が存在しますが、その使用方法は以下のように異なります。
◆「オプション」→「鉄筋基準値」
この画面で設定する継ぎ手長は、簡易入力から詳細入力を生成する際に使用されます。
例えば、たて壁主鉄筋に継ぎ手が必要な場合や、底版下面主鉄筋の継ぎ手長の設定に使用します。(配力筋には、使用しません。)
◆「オプション」→「作図設定」→「材料基準値」
この画面で設定する継ぎ手長(ラップ長)は、生成実行段階で配力筋に継ぎ手が生じた場合に使用します。 |
| |
|
| Q8. |
底版折れ形状の場合、継ぎ手が配力筋に生じないのはなぜか? |
| A8. |
平面折れの擁壁の配力筋継ぎ手に関しては、複数の考え方がある為、現在はサポートしておりません。お手数お掛けしますが、設計に応じて、UC-Drawで編集して頂くよう御願いします。 |








