| �@�Q�D�v�Z |
| �@�@�@�@�@�@ |
|
| �p�Q�|�P�D |
���ނ̑ϋv���\�̏ƍ����s���ɂ͂ǂ�������悢���B |
| �`�Q�|�P�D |
���ނ̑ϋv���\�̏ƍ��́A�i����p�x�z�̇@D�̃P�[�X�y��1.00(D+L+PS+CR+SH+E+HP+U)�̃P�[�X�ɑ��ďƍ����s���܂��B
�u�i���^�ϓ���p���̉d�P�[�X�v�ɂ����āA�i�i���jD�̃P�[�X�y��1.0(D+L)�̃P�[�X���I������Ă��邩���m�F���������B�܂��A1.0(D+L)�̃P�[�X�ɂ����Ă͑ϋv���̏ƍ����s�����ǂ����̑I��������܂��̂Łu�ϋv���̏ƍ��v�Ƀ`�F�b�N�����Ă��������B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�Q�D |
1.0(D+L)��D+L�����邪�A1.0(D+L)�͂ǂ������P�[�X���B���H���������E������T�̑g�����ɋL�ڂ͂Ȃ��B |
| �`�Q�|�Q�D |
�ϋv���\�y�ъ�b�̐v���̕ψʂ̐����ƍ��ɂ����ĕK�v�ȃP�[�X�ƂȂ�܂��B
����29�N���H���������E������V P.187�y�ѕ���29�N���H���������E������W P.167�����m�F���������B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�R�D |
�㕔�H�������͂ɉd�W����qD, �g�����W����pD���l������Ă���̂͂Ȃ����B |
| �`�Q�|�R�D |
���䑤�œ��͂���㕔�H���͂ɂ��ẮA�W�����l�����Ȃ��l����͂��܂��B
�㕔�H�������͂ɂ����ẮAH29���H���������X P.81�̊����͂ɂ����āA���d�iD�j�̑g�����W���y�щd�W�����l����A�n�k�̉e���iEQ�j�̑g�����W���y�щd�W�����l������ƋL�ڂ����邽�߁A�v�Z���ɗ����̌W�����l�����Đv���s���܂��B����āA�d�W����qD, �g�����W����pD���l�������l�ƂȂ�܂��B
���A�㕔�H�������͂ɂ����ČW�����l�����Ȃ��ꍇ�́A�u�d�v�|�u�㕔�H���́v��ʂ́u�n�k���iEQ�j�v�̐�������H�ł͂Ȃ��u���̑��v�̐�������H�ɒl����͂��Ă��������B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�S�D |
���ڊ�b�̈���ƍ��ɂ����āA���E���1�̌��ʂɒn�Ք��͓x�̌��ʂ��\������邪�A�����l���o�[�\���ƂȂ��Ă���̂͂Ȃ����B |
| �`�Q�|�S�D |
����29�N���H���������W P.204�ɂ����āA��Ղ̏ꍇ�͉����n�Ք��͓x�̏ƍ��A��ՈȊO�͉����x���͂̏ƍ��Ɋւ���L�q���������܂��B�{���i�͂���ɏ]���Ă���܂��B
�������͉�ʂ̎x���n�Ղ̑I���ɂ��ƍ����e���ς��܂��B�܂��A��ՈȊO�̏ꍇ�A�n�Ք��͂̏ƍ����s��Ȃ����߁A�����l���o�[�\���Ƃ��Ă���A�n�Ք��͓x�݂̂�\�����Ă���܂��B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�T�D |
�ϋv���\�̉��͓x�̈�����ύX����ɂ́A�ǂ��ŕύX����̂��B |
| �`�Q�|�T�D |
�u�ޗ��v�|�u��́v��ʂ̕��ނ̎�ނň�ʕ��ށC�C�����ށC�������ނ�ύX���Ă��������B
���͓x�ɂ��ẮA�u��l�v��ʂ́u�S�v���ڂɋL�ڂ�����܂��B
�܂��A���|�ł́A��ʕ��ވ����Œ�ƂȂ�܂��B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�U�D |
���ڊ�b�̈���ƍ��ɂ����āA�x���n�Ղ���Ղ̂Ƃ��ɉ����x���͂̌v�Z�͍s��Ȃ��̂��B�܂��A�Ζʏ��b�̏ƍ��ɂ����Ă���Ղ̏ꍇ�́A�����n�Ք��͓x�̂ݍs���悢�̂��B
|
| �`�Q�|�U�D |
����29�N���H���������W 9.5.2(P.204)�ɂ����āA��Ղ̏ꍇ�͉����n�Ք��͓x�̏ƍ��A��ՈȊO�͉����x���͂̏ƍ��Ɋւ���L�q���������܂��B
�������A�x���n�Ղ���Ղ̏ꍇ�ł������x���͂̏ƍ����K�v�ȃP�[�X�ɂ����ẮA�u�������́v��ʂ̍l�����^�u�Łu�����x���͂̏ƍ��v���u�L��v�Ƃ��邱�Ƃŏƍ����s�����Ƃ��\�ł��B
�܂��A�Ζʏ��b�ɂ����ẮA�v�v�̑��W�@�������ݕ҂ɏ����������̂ƂȂ�܂��̂ŁA�n�Ք��͓x�݂̂��s���悢���ɂ��Ė��m�ȉ��s�����Ƃ��ł��܂���B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�V�D |
�ϋv���\�̏ƍ����̂���f�͂���p����|�ނ̈������͓x�i��J�j��s�ƍ��ɂ����āA999.999���\�����ꔻ�肪NG�ƂȂ闝�R�͂Ȃɂ��B |
| �`�Q�|�V�D |
����f�⋭�����S���邹��f�͂̍��vSs>0�̏ꍇ�ł���f�⋭�S�������͂̏ꍇ�́A��s��999.999�Ƃ��Ĕ��肪NG�ƂȂ�܂��B����āA����f�⋭�̓��͂��K�v�ƂȂ�܂��̂Ŋe���ޔz�؉�ʂɂ����Ă���f�⋭�̓��͂��s���Ă��������B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�W�D |
�u�v�v�̑��W �������ݕҁv�ɋL�ڂ������������h�~�쓮���̕��ޏƍ��͉\���B |
| �`�Q�|�W�D |
�����h�~�쓮���̕��ޏƍ��ɂ��ẮA�u����29�N���H���������v�ɋL�ڂ��Ȃ����ߌ������s�����Ƃ��ł��܂���B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�X�D |
���ڊ�b�̎x���͂̏ƍ��ŁA����Fr���}�C�i�X�ƂȂ�ꍇ������͉̂��̂��B |
| �`�Q�|�X�D |
���͂��}�C�i�X�̕����ɂȂ�P�[�X�́A���{���H����̃z�[���y�[�W�́u���H���������E������@�W�����\���ҁv�̎���E��(No.IV-9-3)�ɋL�ڂ��������܂��B
���͂����ɂȂ�P�[�X�́A����29�N���H���������W�����\���҂̎�(9.5.3)�̕��ꂪ���ƂȂ�ꍇ�ŁA��b��ʂɍ�p���鐅���͂���b��ʂƒn�ՂƂ̊Ԃɓ����ő傹��f��R�͂̓����l�Ɣ�r���đ傫�������A�����������ψʂ������Ă�����A�]�|���[�����g�ɂ��ΐS���������͂̍�p�ʒu����b��ʂ̒��S����ɒ[�ɗ���s��������]�|���������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�P�O�D |
�t�[�`���O�����̏ƍ��ŁA�n�k�̉e�������̂v�Z���Ă��闝�R�͉��̂��B |
| �`�Q�|�P�O�D |
����29�N���H���������W P.127�ɂ����āA�����n�Ք��͌W��kv�͒n�k�̉e�����܂܂Ȃ��ꍇ�̒l�Ƃ���ƋL�ڂ���܂��B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�P�P�D |
����f�X�p����ɂ��R���N���[�g�̕��S�ł��邹��f�͂̊����W��cdc�ɂ�����a/d��2.5�ȉ��ɂ��ւ�炸�A�ucdc=1.000�v�ɂȂ��Ă���̂͂Ȃ����B |
| �`�Q�|�P�P�D |
�u����29�N���H���������Ɋ�Â����H���̐v�v�Z��v P.484�ɂ����āA�v�f�ʈʒu���Y�ʒu���O���ɂ���ꍇ�́A����f�X�p������l�����Ȃ����Ƃ��1.0�Ƃ��Ă���܂��B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�P�Q�D |
�C�Ӊd�ɍl�������d�W���A�g�����W�����m�F�������B�W�v�\���m�F���Ă��o�[�\���ƂȂ��Ă���B |
| �`�Q�|�P�Q�D |
�C�Ӊd�ɂ��ẮA�����̉d��ʂ��g�ݍ��킹�\�ł��̂ŁA��p�͏W�v�ł̓o�[�\���Ƃ��Ă���܂��B
���ʏڍv�Z���́u��̎��d�C �y���d�ʁC ���́C ���̑��d�ɂ�鉔���́A�����́v�́u(3)���̑��d�v�̏o�͂����m�F���������B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�P�R�D |
���p�����̌����ɂ����āA����ƍ����s�����Ƃ͂ł��邩�B |
| �`�Q�|�P�R�D |
����ƍ��͉\�ł��B
���p�����̈���ƍ��̗L���ɂ��ẮA�I���ƂȂ��Ă��܂��B
�u�d�v�|�u�d�̈����v��ʂɂ����āu���p�����̍�p�P�[�X���w�肷��v�Ƀ`�F�b�N����ꂽ��A�u�l�����v�|�u����v�Z�v��ʂɂāu���p�����̈���v�Z�v��L��Ƃ��Ă��������������B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�P�S�D |
�t�[�`���O�̂���f�ƍ��ʒu�ɂ����āAH/2���O���ɍY�������ꍇ��H/2�ʒu���ƍ��ʒu�Ƃ��Ă��闝�R�͂Ȃɂ��B |
| �`�Q�|�P�S�D |
�t�[�`���O�̂���f�ƍ��ʒu�ɂ��ẮA�u����29�N���H���������Ɋ�Â����H���̐v�v�Z��vP.481-490�ł́A�Y��H/2���O���ɂȂ��ꍇ�ł�����f�ƍ����s���Ă��܂��B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�P�T�D |
�t�[�`���O�̒��o���̏ƍ����s�������B |
| �`�Q�|�P�T�D |
�u�`��v - �u��́v - �u���ʌ`��v�ɂ����č��E�̒��o�����w�肵�A�u���o���̏ƍ��v���u�L��v�Ƃ��鎖�ŏƍ����s���܂��B�Ȃ��A�u�l�����v - �u��Őv�v��ʂ́u���p�����̕��ސv�v�Łu���������̉d�v�Ƀ`�F�b�N�����鎖�ŋ��������̒n�Ք��́A�Y���͂�p���Đv���s�������\�ł��B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�P�U�D |
�O�ʓy���̎y���͂ǂ̏ƍ��Ŏg�p�����̂��B |
| �`�Q�|�P�U�D |
���ڊ�b���ɂ�����u��b�̍����ꕔ���ɍ�p���鐅���d�̏ƍ��v�ɉe��������܂��B���̎��A�����d�ɑ����R�͂Ƃ��đO�ʎy�����l������܂��B�O�ʎy�����l���������ꍇ�́u��b�v��ʂɂāu���������̑O�ʎy�����l���v�Ƀ`�F�b�N�����Ă��������B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�P�V�D |
�w1.0(D+L)�x�Ƃ����d�P�[�X�́A���d(D+L)�P�[�X�ƁA��p�͂ɈႢ���o��̂��B |
| �`�Q�|�P�V�D |
D+L�P�[�X��1.0(D+L)�P�[�X�ł͍�p�͂ɑ��Ⴊ�����܂��BD+L�ł́A����29�N���H���������T P.49�̕\-3.3.1�̂悤�ɍ�p�̑g�����ɉ������d�W����g�����W�����l��������p�͂��Z�o���܂����A1.0(D+L)�ł́A�����̌W����1.0�Ƃ��č�p�͂��Z�o���܂��B
��p�͈ȊO�ɂ��قȂ�ƍ����e������܂��̂ŁA�p�Q�|�Q�D�����킹�Ă������������B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�P�W�D |
�Y���͂���ʏ�Ŋm�F���邱�Ƃ͂ł��邩�B |
| �`�Q�|�P�W�D |
���ʊm�F�́u����v�Z�v�|�u�Y���̓f�[�^�v��ʂɂāAKv�l�A�Y���̓f�[�^���m�F���邱�Ƃł��܂��B
���А��i�u��b�̐v�E3D�z��(�����W���@�EH29�����Ή�)�v��u�[�b�t���[���E3D�z��(�����W���@�EH29�����Ή�)�v�ƘA�����Ă���ꍇ�����l�ł��B
�܂��A�A�����ɏ�L��ʂɍY���͂����f����Ȃ��ꍇ�́A��b���̈���v�Z�����v�Z��ԂłȂ����m�F���Ă��������B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�P�X�D |
�n�k���y���̏C�������E�������ɂ����āA�v�����k�x�ɉd�g�����W���y�щd�W���ɓy���iE�j�ƒn�k�̉e���iEQ�j���l������L�ڂ�����̂͂ǂ����B |
| �`�Q�|�P�X�D |
�u����29�N���H�������� �X�ϐk�v�ҁv P.101�ɂ����Ď��ɓy��(E)�A�v�����k�x�ɒn�k�̉e���iEQ�j���l������L�ڂ�����܂��B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�Q�O�D |
��dSW�́A���H���������T P.49 ��p�g������D+L�AD+L+TH�AD+TH+EQ�ȊO�ɑg�ݍ��킹�邱�Ƃ͉\���B |
| �`�Q�|�Q�O�D |
��dSW�ɂ��܂��ẮAD+L�AD+L+TH�AD+TH+EQ�ȊO�ł��l�����邱�Ƃ͉\�ł��B
�����ɋL�ڂ���Ă���g�����ȊO�ƂȂ�܂��̂Ōv�Z���s���Ƀ��b�Z�[�W���\������܂����A�d�W���E�g�����W����1.0��p���Čv�Z�ɍl�����܂��B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�Q�P�D |
�����ߓy�ɔS���͂�ݒ肵���ꍇ�̓y����p���̌v�Z�ɂ��āA�y�������y���S���ƂȂ�Ȃ��͉̂��̂��B |
| �`�Q�|�Q�P�D |
�S���͂�����ꍇ�̍�p���́A�ȉ��̂悤�Ɍv�Z���܂��B
����29�N���H���������E������T ���ʕ� P.116
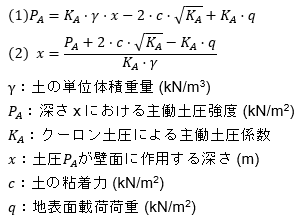
�[��x�ɂ�����哭�y�����x��(1)���ɂ��Z�o����܂����A���̂Ƃ���S���͂ɂ��哭�y���͒ጸ����܂��B
�v�Z��A�y�����x�����ɂȂ�͈͂��o��ꍇ������A�y����0�ƂȂ�[����(2)���ɂ��Z�o����܂��B
�y�����x�����ƂȂ��Ԃ͎哭�y�����������Ȃ����̂Ƃ��Ĉ����܂��B
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�Q�Q�D |
�Y��b�̐v�ɂ����āA�u��b�̐v�E3D�z��(�����W���@�EH29�����Ή�)�v���i�ƘA������Ɖ\�ƂȂ鍀�ڂ͉����B |
| �`�Q�|�Q�Q�D |
�Y�A�����s�����Ƃʼn��L�̍��ڂɑ���v���s�����Ƃ��ł��܂��B
- ���x���Q�n�k���ɂ��v
- �n�w�ɌX������ꍇ�̌���
- �Y�̒������قȂ�ꍇ�̌���
- 2.5������͂ɂ�錟��
- �Y��̃n�C�X�y�b�N�}�C�N���p�C���Ή�
- �Ζʂ̌X���l�������n�Ղ˂̒ጸ�ƍ�
- ���w�x���Y�̎����v�Z
- �Q�Y�̏ƍ�
|
| �@ |
|
| �p�Q�|�Q�R�D |
��łɎΊp��݂����ꍇ�A�v�Z��ł��Ίp���l�������v�Z�ƂȂ�̂��B |
| �`�Q�|�Q�R�D |
��łɎΊp��݂����ꍇ�ɂ����Ă��A�v�v�Z��͋�`�Ƃ��Ď�舵���܂��B
�u�`��|��́v��ʂ̐v�f�ʈʒuBC, HC����f�ʐ��@���擾���A��`�Ɋ��Z���Čv�Z���s���܂��B
����ʃw���v�u�����ʌ`��v�̋L�q�����킹�Ă��m�F���������B
|








