| �@�P�D�K�p�͈́A���� |
| �@ |
|
| �p�P�|�P�D |
�������E�⋭�v�ɑΉ����Ă��邩�B
|
| �`�P�|�P�D |
���݂͑Ή����Ă���܂���B
H29������K�p�����������E�⋭�v�Ɋւ���Q�l�������ނ̔�����ɑΉ�����������\��ł��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�Q�D |
���f�[�^�̓ǂݍ��݂͉\���B |
| �`�P�|�Q�D |
�u���[����������̐v�v�ZVer.6�v�ȍ~�̐v�f�[�^��ǂݍ��ނ��Ƃ��ł��܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�R�D |
�u�i���^�ϓ���p���̉d�P�[�X�v��ʂ̉d��Ԃ̉��́u����ƍ��v�y�сu�ϋv���\�v�͂ǂ̂悤�ȂƂ��ɗL���ɂȂ�̂��B |
| �`�P�|�R�D |
�ϋv���\�y�ъ�b�̐v���̕ψʂ̐����ƍ��ɂ����ĕK�v��1.0(D+L)�̃P�[�X��I�������ۂɗL���ɂȂ�܂��B
1.0(D+L)�̃P�[�X�ɂ��ẮA����29�N���H���������E������V P.187�́u6.3.2�ϋv���\�̊m�ہv(2)�y�ѕ���29�N���H���������E������W P.167 �u8.2�v�̊�{�v(3)2)�����m�F���������B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�S�D |
�����ڂ�����ɑΉ����Ă��邩�B |
| �`�P�|�S�D |
���݁A����29�N���H���������ɑΉ������u�v�v�̑��W�@�������ݕҁv����X�V����Ă��Ȃ����߁A�����ڂ�����ɂ�����ƍ��ɑΉ����Ă���܂���B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�T�D |
�Ζʏ��b�̌v�Z�ɑΉ����Ă��邩�B |
| �`�P�|�T�D |
���݁A����29�N���H���������ɑΉ������u�v�v�̑��W�@�������ݕҁv����X�V����Ă��Ȃ����߁A�Ζʏ��b�̌v�Z�ɑΉ����Ă���܂���B�܂��A ����29�N���H���������W P.204�ł́A��Ղ̏ꍇ�ɉ����n�Ք��͓x�̏ƍ����s�����Ƃ��L�ڂ���Ă���܂��̂ŎΖʏ��b�̎x���͂ɂ��ƍ��͂����Ȃ��Ă���܂���B
��ɂ��Ζʏ��b�̌v�Z���@�����m�ɂȂ�܂�����A�{���i�ɂ����Ă������Ή��������܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�U�D |
�k�x�Z�o�i�x���v�j(�����W���@�EH29�����Ή�)�ɂ����āA�n�Վ�ʂ̔�����o�͂���ɂ͂ǂ�����悢���B |
| �`�P�|�U�D |
���P�Ƃ̏ꍇ
�@�n�Վ�ʎZ�o�p�̐v�����́A�u�������́v��ʂ́u�ޗ��E�d�v�́u�d�i�v�k�x�j�v�ɂ����܂��āA�n�Վ�ʂ̉��́u�����v�{�^���̐ݒ肩��J���u�n�w�f�[�^�v��ʂɒl��ݒ��A�v�Z�m�F��������ʂ��m�肵�Ă��������B
����b�ƘA�����Ă���ꍇ
�P�D�u�������́v��ʂ́u�n�Վ�ʂ̔����A������v�Ƀ`�F�b�N���Ȃ��ꍇ
�@�P�Ƃ̏ꍇ�Ɠ��l�ɐݒ肵�܂��B
�Q�D�u�������́v��ʂ́u�n�Վ�ʂ̔����A������v�Ƀ`�F�b�N������ꍇ
�@��b���œ��͂����n�Վ�ʂ����䑤�ɘA�����܂��B�n�Վ�ʂ̔���́A��b���́u�n�w�v��ʂ̌v�Z�����ɂāA�t�̔�����̒n�Վ�ʂœ����v�Z���s�����ꍇ�ɏo�͂���܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�V�D |
�u�k�x�Z�o�i�x���v�j�i�����W���@�EH29�����Ή��j�v�ƐV�K�ŘA�g����ɂ́A�ǂ̂悤�ɓ��͂���悢���B |
| �`�P�|�V�D |
�@�����H�f�[�^�̍쐬
1.�����H�v���_�N�g���N�����A�K�v�ȓ��͂���яC�����s���܂��B
2.���͌�A���C����ʂ̏������[�h�̑I���̐k�x�A�g�ւ̃{�^�����������A�t�@�C�����j���[�́u�t�@�C���ɖ��O��t���ĕۑ��v��I�����܂��B
3.���O��t���ĕۑ��_�C�A���O�ł́A�t�@�C���̎�ނ��u�k�x�Z�o�i�x���v�jXML�`��(*.PFU)�v�ƂȂ��Ă���̂��m�F���Ă��������B
�@�@�t�@�C���̎�ނɑ��Ⴊ����ꍇ�́A2.�̏������[�h�̑I���̐k�x�A�g�ւ̃{�^�����������ēx3.�����s���Ă��������B
4.�ۑ��{�^����������A�\�����ɖ��O��t���ĕۑ��_�C�A���O���\������܂��̂ō\��������(A1, A2���j����͂��܂��B
�A�����f�[�^�̍쐬
1.�u�k�x�Z�o�i�x���v�j�i�����W���@�EH29�����Ή��j�v�ɂāA�ۑ������t�@�C���u*.PFU�v���J���A���������\���C�P����\���̓��͂��s���܂��B
�@��PFU�t�@�C���ɂ́A�u�\�����`��̓o�^�b�����\���v�ɇ@�̎菇�ō쐬�ۑ����ꂽ�����H�������o�^����Ă��܂��B
�B�v�Z���s
1.�u�k�x�Z�o�i�x���v�j�i�����W���@�EH29�����Ή��j�v�ɂāA�v�Z�����s���܂��B
�C�f�[�^����ьv�Z���ʂ̌���
�v�Z���s�ɂ�艺���H�v���_�N�g���Őݒ肵�Ă���v�����k�x�Ɓu�k�x�Z�o�i�x���v�j�i�����W���@�EH29�����Ή��j�v�ŎZ�o���ꂽ�v�����k�x���傫���قȂ�ꍇ�́A�����H�f�[�^���C�����A��͂��J��Ԃ��K�v������܂��B
1.�v�Z���s��A��r�\���m�F���A�u�k�x�Z�o�i�x���v�j�i�����W���@�EH29�����Ή��j�v���ŏ㏑���ۑ������s���Ă��������B
�D�����H�f�[�^�̏C��
1.�����H�v���_�N�g���A�t�@�C�����j���[�́u�t�@�C�����J���v��I�����܂��B
�@���t�@�C�����J���_�C�A���O�ł́A�t�@�C���̎�ނ��u�k�x�Z�o�i�x���v�jXML�`��(*.PFU)�v��I�����Ă��������B
2.�t�@�C����I����A�J������������ƁA�\�������J���_�C�A���O���\������܂��̂œǂݍ��݂����\�����iA1,A2���j��I�����܂��B
3.�u�k�x�Z�o�i�x���v�j�F�v�Z���ʂ̎Q�Ɓv��ʂ��\������܂��̂ŁA�u�捞�v�{�^�����������܂��B
�@���v�Z���ʂ̔�r�\���\������A�ԕ��������Ⴊ������͂ƂȂ�܂��B�k�x�Z�o���Ōv�Z�����l�������H�v���_�N�g�Ɏ�荞�݂����ꍇ�́A�u�捞�v�{�^������������Ɠ��͒l�Ɏ����I�Ɏ�荞�܂�܂��B
4.�����H�v���_�N�g�Ōv�Z�����s���A���ʂ�NG�ƂȂ�Ό`���z�ؓ��������������s���܂��B
5.�����H�v���_�N�g�ŏ㏑���ۑ������s���܂��B
6.���ׂẲ����H�v���_�N�g�Ō��������I����A�u�k�x�Z�o�i�x���v�j�i�����W���@�EH29�����Ή��j�v��5.�ŕۑ������t�@�C���u*.PFU�v���J���A�ēx�B�̐k�x�Z�o���Ōv�Z�����s���A�C�C�D���J��Ԃ����Ƃʼn����H�v���_�N�g��NG�ƂȂ�Ȃ��悤���܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�W�D |
���x��2�n�k���̎x���̐������͂ɂ��āA0.45�{����P�[�X�Ƃ��Ȃ��P�[�X�̋�ʂ͂ǂ̂悤�ɍl���ē��͂���̂��B |
| �`�P�|�W�D |
���H���������X P.261��0.45�{�̋L�ڂɂ��ẮA������P.247�̉��(1)���Œ�x����e���x���̏ꍇ�ɂ́A���x���Q�n�k������p�����Ƃ��̎x���̐������͂��l������Ƃ��邱�Ƃ���A0.45�{���l�������l����͂��܂��B�܂����x���̏ꍇ�́A4.1.1(5)�̋L�ڂƂȂ邱�Ƃ���0.45�{�͍l�����Ȃ��l����͂��܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�X�D |
�㕔�H���͂̎��d�C���d�C�n�k�͈ȊO�̔��͂��l������ɂ͂ǂ�����悢���B |
| �`�P�|�X�D |
�u�㕔�H���́v��ʂ̃P�[�X�ɂ����āA�u�ڍד��͂��s���v�Ƀ`�F�b�N�����A�d�����w�肵�Ă��������B
���̌�A�u��ʁv��I�����Ēl����͂��܂��B�u��ʁv�ł́A�d�g�����ɂđI�������d�őg�����邱�Ƃ��\�ȉd���\������܂��B
�g�����邱�Ƃ��\�ȉd�́A����29�N���H���������T P.47�̋L�ڂ̉d�ƂȂ�܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�P�O�D |
�Y��b�A���ɂ�����2.5������͂��s���������A��b���́u�v�Z�����v��ʂőI�����O���[�ƂȂ��đI�����ł��Ȃ��B
|
| �`�P�|�P�O�D |
�u�Y��b�̘A���ɂ�����2.5������͂��s���ɂ́A���䑤�́u�������́v��ʂ̊�b�`���Łu�Y��b�i2.7������́j�v��I�����Ă��������B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�P�P�D |
���ڊ�b�̊�b�˂ɂ����āA�v�Z�ߒ���\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����B |
| �`�P�|�P�P�D |
�u��b�v��ʂ̍����́u��b�ˎZ�o�p�f�[�^�v��ʂɂ����Ċ�b�ˎZ�o���@�������ݒ��I�����Ă��������B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�P�Q�D |
��b�A�����Ɋ�b���̓��͂Ƌ��䑤�̓��͂ƈقȂ�ꍇ�̑Ώ����@�������Ăق����B |
| �`�P�|�P�Q�D |
��b���̓��͂ƈقȂ�ꍇ�́A���䑤�Ŏ��̕��@�ɂđ�����s���Ă��������B
- ��̌`����Ő��@���قȂ�ꍇ
�u�`��v�|�u��́v��ʂ��m�肵�Ă��������B
- �S��R���N���[�g�ގ����قȂ�ꍇ
�u�ޗ��v�|�u��́v��ʂ��m�肵�Ă��������B
- �y���␅�̒P�ʑ̐Ϗd�ʂ��قȂ�ꍇ
�u�ޗ��v�|�u�y���E���v��ʂ��m�肵�Ă��������B
- ��p�P�[�X�����قȂ�B
�u�d�v�|�u�i���^�ϓ���p���̉d�P�[�X�v��ʂ��m�肵�Ă��������B
�A�����i�Ԃ̑���ɂ��ẮA��b���̉�ʂ��J������Ԃŋ��䑤�̌`���d��ύX������ɁA��b���̉�ʂ��m�肷��Ɣ������邱�Ƃ�����܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�P�R�D |
�Y��b�A�����ɂ����āA�d�P�[�X�������k���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ͂ł��邩�B |
| �`�P�|�P�R�D |
�Y��b�A�����ɂ����āA�u��b�v�|�u�d�̈����v��ʂɂ����ĉd�P�[�X�̈��k������^���Ȃ�(�������ꍇ�݈̂��k)�̑I�����\�ł��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�P�S�D |
�Y���͂���ʏ�Ŋm�F���邱�Ƃ͂ł��邩�B |
| �`�P�|�P�S�D |
���ʊm�F�́u����v�Z�v�|�u�Y���̓f�[�^�v��ʂɂāAKv�l�A�Y���̓f�[�^���m�F���邱�Ƃł��܂��B
���А��i�u��b�̐v�E3D�z��(�����W���@�EH29�����Ή�)�v��u�[�b�t���[���E3D�z��(�����W���@�EH29�����Ή�)�v�ƘA�����Ă���ꍇ�����l�ł��B
�܂��A�A�����ɏ�L��ʂɍY���͂����f����Ȃ��ꍇ�́A��b���̈���v�Z�����v�Z��ԂłȂ����m�F���Ă��������B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�P�T�D |
�n�k�������u�O����v�Ƃ��Čv�Z���s�������B |
| �`�P�|�P�T�D |
�u�d�v�|�u�i���^�ϓ���p���̉d�P�[�X�v��ʂ̒n�k���̃P�[�X�ɂ����āA�n�k�������u�O����v�Ƃ��Ă��������������B
���A������p���̌����́A�n�k���̕����́u�O����v�ƂȂ�܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�P�U�D |
�i���t�[�`���O�̐v���s�������B |
| �`�P�|�P�U�D |
�u�������́v��ʂ��A�u��b�`���v�́u�i���t�[�`���O�v�Ƀ`�F�b�N�����ĉ������B���̌�A�u�`��v-�u��́v��ʂ́u�i���`��v�^�u�ɂĐ��@���͂��s���܂��B�Ȃ��A���������݂̂̌������\�ł��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�P�V�D |
���ǂ���ы��ǂ�D+TH+EQ�P�[�X�̒f�ʌv�Z���s�������B |
| �`�P�|�P�V�D |
�������͉�ʂ́u�l�����v�|�u���ނ̉��x�d�iD+TH+EQ)�v�Łu�l������v��I�����ĉ������B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�P�W�D |
�u�l�����v�|�u�y���E�����v��ʂ́u�y���Z�o���̐��ʂ̈����v�́u�l������v�Ɓu���������v�̈Ⴂ�͉����B |
| �`�P�|�P�W�D |
�u�l������v��I�������ۂ́A���ʂ��w�肷��ƕK�����ʈȉ��̓y���͐����d�ʂŌv�Z���܂��B
�u���������v�ł́A�w�ʐ������l������P�[�X�ɂ����Đ��ʈȉ��̓y���͐����d�ʂŌv�Z���܂��B
�]���āA���ʂ�����ꍇ�ɐ�����K���l������ꍇ�͗��҂Ƃ��������ʂƂȂ�܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�P�X�D |
�G�ǁA���ǂɑO�ʓˋN��݂������B |
| �`�P�|�P�X�D |
�u�`��v�|�u��́v��ʂ̑��ʌ`��̑O�ʓˋN������Ƃ��Ă����͉������B
���A�G�ǑO�ʓˋN������ꍇ�̒G�Ǎ������y�щE�����ɂ́A�O�ʓˋN���������G�ǑO�ʈʒu�̍�������͂��܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�Q�O�D |
�������ʂ�ݒ肵�����B |
| �`�P�|�Q�O�D |
�u�������́v��ʁu�ޗ��E�d�v�^�u�̐��ʂ̎w��ڎw��Ƃ��A�u�d�|���ʁv��ʂł����͂��������B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�Q�P�D |
�w�ʓy�����l�����Ȃ�����̐v�͉\���B |
| �`�P�|�Q�P�D |
�y�����l�����Ȃ����@�Ƃ��āA���L��2���������܂��B
1�D�y�����l�����Ȃ�������ݒ肷��
(1)�u�`��v�|�u�y���E�ܑ��v��ʂɂ����āA�y�����l�����Ȃ������ɋ��䍂���w�肷��
2�D�C�ӓy����p���Đݒ肷��
(1)�u�d�v���u�d�̈����v��ʂɂ����āA�u�C�ӓy���̒��ڎw��v���`�F�b�N�i���j���܂��B
(2)�u�d�v���u�C�ӓy���v��ʂɂ����āA�P�[�X����0�Ƃ��܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�Q�Q�D |
�㕔�H���͂̓��͂ɂ��āA���������ƒ��p�����ɏ㕔�H�������͂���͂���Ɠ����ɗ��������l�������v�Z�ɂȂ�̂��B |
| �`�P�|�Q�Q�D |
��������ƍ������̏㕔�H�������݂͂̂��l���������܂��B
����āA���������ƍ����ɂ́A���p�����̏㕔�H�������͓͂����ɂ͍l�����܂���B�t�����l�ƂȂ�܂��B
�ƍ������́A�u�i���ϓ���p���̉d�P�[�X�v��ʂ̏ƍ��ΏۂŎw�肵�܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�Q�R�D |
���Ǎ��ō����Ƃ��鎖�͉\���B |
| �`�P�|�Q�R�D |
�u�`��v�|�u��́v��ʂ̔w�ʌ`��ɂ����āA��Ǎ��E�������Ǎ��E���Ɠ��������Ƃ��ĉ������B
���ɌX��݂���ꍇ�A�X�Ε��̍�����������Ǎ�������͂��Ă��������B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�Q�S�D |
�㕔�H���͂�n�\�ʉd�ɂ����āA��d�̓��͂��s�����Ƃ��ł��邩�B |
| �`�P�|�Q�S�D |
��d�ɂ��ĉ��L�̓��͂�lj����܂����B(Ver.3.1.0)
- �㕔�H���́F���H���������T�@P.47�̍�p�̑g�����ȊO�ł���dSW�̃P�[�X���l���ł���悤�ɂ��܂����B
��p�̑g�����ȊO�̃P�[�X�ł́A�d�W���E�g�����W����1.0�Ƃ��Čv�Z�ɍl�����܂��B
��d�̊����͍�p�ʒu�́A�㕔�H���͍�p�ʒu�ƕʂɎw��ł��܂��B
- �n�\�ʉd�F�n�\�ʉd�Ɠ����d�W���E�g�����W����p����ꍇ�͒n�\�ʉd�ɐ�d����͂��܂��B��d�̉d�W���E�g�����W����p����ꍇ�́A��d�ɓ��͂��܂��B
- ���ǐv��ʁ@�F��d�̓��͂�lj����܂����B���ǁA��A���|�łɂ����āA��p�͌v�Z���ɐ�d�̉d�W���E�g�����W����p���Čv�Z���s���܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�Q�T�D |
��b�˂̒l�ڎw�肵�����B |
| �`�P�|�Q�T�D |
��b�˂͐k�x�A�g���[�h�̏ꍇ�ɎZ�o����܂��B���ڊ�b�̂Ƃ��Ɋ�b�˂ڎw�肷��ɂ́A�u��b�v��ʂ́u��b�ˎZ�o�p�f�[�^�v��ʂɂ����Ď����v�ƒ��ڎw����ւ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�܂��A�Y��b�̂Ƃ��ɂ́A�u��b�v�|�u��b�̈����v��ʂɂ����Ď����v�ƒ��ڎw����ւ��邱�Ƃ��ł��܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�Q�U�D |
��̉�ʂ̌`�@�ɂ��āA�͈͊O�̓��͂����Ă����͂Ȃ����H |
| �`�P�|�Q�U�D |
��̌`��̓��͔͈͂ɂ��܂��Ă͈�ʓI�ƍl������͈͂�ݒ肵�Ă��܂��B
�͈͊O�̐��l����͂����ꍇ�͐ԕ\���ƂȂ�܂����A�`��Ɋւ��Ă͔͈͊O�̒l�ł�����Ƃ��Ă̌`�\������Ă���Ζ��Ȃ��v�Z�\�ł��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�Q�V�D |
���ǂ̔z�f�[�^���R�s�[���邱�Ƃ͂ł��邩�B |
| �`�P�|�Q�V�D |
�u���ǔz�v��ʂɂăE�B���h�E�����́u�R�s�[�v�{�^�����������ƂŁA�I�𒆂̗��ǂ̔z�f�[�^�������Б��ɃR�s�[���邱�Ƃ��ł��܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�Q�W�D |
��łɎΊp������ꍇ�̍Y��b�ɂ����āA��b�A�����̒�Ő��@�̈������͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩�B
|
| �`�P�|�Q�W�D |
����ɎΊp��݂����ꍇ�Y�z�u�̌v�Z���f���Ƃ��Ă̎�舵�����́A�u��b�v - �u��b�̈����v��ʂɂāA3�^�C�v����ݒ�����邱�Ƃ��ł��܂��B
��b�A�����ɂ́A�^�C�v�̐ݒ�ɂ���b���ł̒�Ő��@�≏�[�����̎�舵�������ς��܂��B
�^�C�v1�F�Ίp�̍l�����A�f�ʐ��@���Z
�u�`��v��ʂŎw�肵������̃��f�����A�����������C���p�������̋�`�Ƃ݂Ȃ��čY��z�u���܂��B

�^�C�v2�F�Ίp�̍l���L�A�f�ʍő吡�@
���p�����Ɋւ��Ď��ۂ̍Y�z�u�ɂ��ƍ����鎞�ɑI�����܂��B���p�������́A�S�Ă̍Y���z�u�ł���悤�ɉ��̂悤�Ɋg�����Ă��܂��B�t�[�`���O���S�ʒu�͒��p�������̔����ɂȂ�܂��B
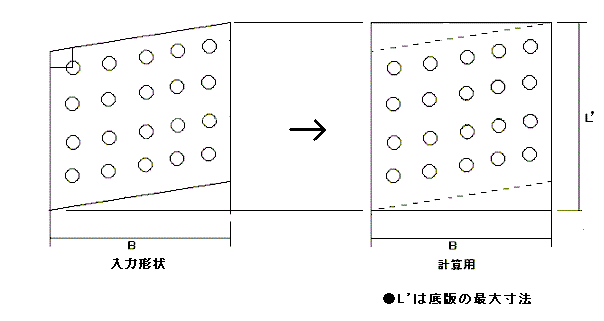
�^�C�v3�F�Ίp�̍l���L�A�f�ʒ��S�ʒu
���p�����Ɋւ��Ď��ۂ̍Y�z�u�ɂ��ƍ����鎞�ɑI�����܂��B���p�������́A�S�Ă̍Y���z�u�ł���悤�Ɂu�`��v��ʂ̒��p�������y�ђf�ʈʒu�ɂ�����Ċg�����Ă��܂��B

|
| �@ |
|
| �p�P�|�Q�X�D |
�Y��b�̃��x��2�n�k���̏ƍ����s�����Ƃ͂ł��邩�B
|
| �`�P�|�Q�X�D |
�u��b�̐v�E3D�z��(�����W���@�EH29�����Ή�)�v�Ƃ̘A�����K�v�ɂȂ�܂��B
��b���i���Ń��x��2�n�k���̍Y��b�̏ƍ����s���܂����A�t�[�`���O(�O��A����A��Œ�����)�̏ƍ��͋��䑤�ōs���܂��B
�܂��A�������p�����ɑ���ƍ����@�͖��m�łȂ����߁A���������̌����݂̂ƂȂ�܂��B
�Ȃ��A��b�A���ɂ�F8 COM Server�̃C���X�g�[�����K�v�ł����A�A�����ɐ��i����C���X�g�[�����邱�Ƃ��\�ł��B
https://www.forum8.co.jp/download/f8com-down.htm
|
| �@ |
|
| �p�P�|�R�O�D |
���ŏ�̓y���Ɣw�ʓy���̒P�ʏd�ʂ����ꂼ��ʂɐݒ肵�����B
|
| �`�P�|�R�O�D |
�u�l����-�y���E�����v��ʂ�[�������]�Łu���ŏ�̓y���̒P�ʏd�ʁv���u�T�Z�d�ʁv�Ƃ��ĉ������B
�u�T�Z�d�ʁv��I�������ꍇ�A���ŏ�̓y���́A���ŏ�̓y���d�ʂŐv����܂��B
�Ȃ��A���ŏ�̓y���̒P�ʑ̐Ϗd�ʂ́A�u�ޗ��|�y���E���v��ʂŎw��\�ł��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�R�P�D |
�Y�̎x���͎Z�o���ɁA�Y�̗L���d�ʂ̈�������ύX�������B
|
| �`�P�|�R�P�D |
�u��b�|�n�w�f�[�^�v��ʓ��́u�Z�o�I�v�V�����v�{�^������J����ʂ��A�����ݗ�Ra�́u�����A�l���A�ȈՎ��v����A��������Pa�́u�����A�l���v�����舵�����@�����ꂼ��I�����鎖���\�ł��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�R�Q�D |
�t���v�ŗ��ǂ̐v���u����́v�ɂčs���ꍇ�A�|�A�\����ɂ͂ǂ̂悤�Ȓl������悢���B
|
| �`�P�|�R�Q�D |
�|�A�\����ɂ��ẮA0<��<0.5�͈̔͂œ��͂��܂��B
�R���N���[�g�ɂ��ẮA�u����29�N���H���������V�vP.46-48�̋L�ڂ��Q�l�Ƃ��ē��͂��Ă��������B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�R�R�D |
�O�ǂɊJ������݂������B
|
| �`�P�|�R�R�D |
�u�`��|��́v��ʂ���A�u�J�����v�^�u�ɂĊJ�����̐��@����͂��Ă��������B
�Ȃ��A�v�Z���s���ɂ͂��̊J�������̎��d�͍T������AFRAME���f���ɂ����镔�ލ����͊J���������T�������f�ʂƂ��Đݒ肳��܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�R�S�D |
�����h�~�\���̏ƍ��ɂ��āA�Ȃ��j��^�̔���ȊO�ɂ���f�j��^�łȂ����ǂ������m�F����ɂ͂ǂ�����悢���B
|
| �`�P�|�R�S�D |
�u�l�����|�����h�~�v��ʂ́u�����h�~�\���v�^�u�ɂāA�u�Ȃ��j��^�̔���( (Myc/h)��Susd )�v�̑I���Ƀ`�F�b�N�����Ă��������B
���H���������X P.292-293�ɂ����ẮA�Ȃ��j��s����ꍇ�iM��Myc�j�ƋL�ڂ�����܂����A���f�Ƃ��Ă���f�j��^�ƂȂ�Ȃ����Ƃ��m�F����ꍇ�́A�u������s���v�Ƀ`�F�b�N�����Ă��������������B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�R�T�D |
�u�C�ӓy���v���w�肷�邱�Ƃłǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��s���邩�B
|
| �`�P�|�R�T�D |
�u�C�ӓy���v���w�肷�邱�ƂŁA�y���̍�p���ڎw�肵����A�y���W����y�����x�ڎw�肵���肷�邱�Ƃ��ł��܂��B
�܂��A�w�ʂ�EPS���̌y�ʐ���y��I�������ꍇ�ɂ����āA�y�����l�����Ȃ��悤�Ȑv���\�ł��B
�w�ʓy�����w�肷��菇�͉��L�̒ʂ�ƂȂ�܂��B
- �u�d�|�d�̈����v���
�u�C�ӓy���̒��ڎw��v�Ƀ`�F�b�N�����Ă��������B
- �u�d�|�C�ӓy���v���
�Q�P�[�X�p�ӂ��A�P�P�[�X�ڂ́u�n�k�e�����v�A�Q�P�[�X�ڂ́u�n�k�e���L�v�Ƃ��܂��B
�e�P�[�X�ɂ����āA�@�@��ʉ��́u�W���Z�o�v���������ēy���W������ݒ肵�܂��B�y���W����y�������������I�ɐݒ肳��܂��B
������y���W���A�y�����x�͕ύX�\�ł��B
- �u�d�|�i���^�ϓ���p���̉d�P�[�X�v���
�e��p�P�[�X�ɓK�p�������C�ӓy���Ƀ`�F�b�N�����Čv�Z���s���Ă��������B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�R�U�D |
�㕔�H���͂��x���ʒu���Ƃɓ��͂���ɂ͂ǂ�����悢���B
|
| �`�P�|�R�U�D |
�u�d�|�㕔�H���́v��ʂ̋��ʐݒ�ɂ����āA�㕔�H���͂̓��͂Łu�x���ʒu���Ɓv��I�����Ă��������B
�I����A�x�����Ǝx�����W���w�肷�邱�Ƃ��ł��A�㕔�H���͂��x�����Ƃ̓��͂ƂȂ�܂��B
���������Ƃ��ẮA�k�x�A�g���[�h������сu�������́v��ʂŁu�㕔�H���͂��d�P�[�X���Ɏw�肷��v�Ƀ`�F�b�N���Ȃ��ꍇ�͎w�肷�邱�Ƃ͂ł��܂���B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�R�V�D |
�����̐v�Ŏ��ۂ̎x���z�u�����R�ʐς������v�Z���邱�Ƃ��ł��邩�B
|
| �`�P�|�R�V�D |
�����̐v�̉�ʓ��ɂ���u�x���z�u�v��ʂ̋@�\���g�����ƂŁA�����ʂ�x���̃A���J�[�{���g�ʒu�Ȃǂ̏��A������T���������v�Z�����x���f�[�^���쐬���邱�Ƃ��ł��܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�R�W�D |
�d�g�����P�[�X�ɒn�\�ʉd���ډׂ������Ȃ��ꍇ�͂ǂ�����悢���B
|
| �`�P�|�R�W�D |
�u�d�|�i���^�ϓ���p���̉d�P�[�X�v��ʂł͕K���C�n�\�ʉd�Ƀ`�F�b�N������K�v������܂��B�d��Ԃɉ����č��ڂ��\������邽�߁A�I�����ڂ������ꍇ�́u�d�|�n�\�ʉd�v��ʂɖ߂�A�K�p��ԂŁu�n�k�e�������^�n�k�e���L��v�̃P�[�X�����邩�����m�F���������B
�܂��A���ۂɍډd�������ꍇ�ł��n�\�ʉd�̑I���͕K�v�ɂȂ�܂��B
�u�������́v��ʂŁu�n�\�ʉd���d�P�[�X���Ɏw�肷��v�̃`�F�b�N���O���čډd��0�Ƃ��邩�A�u�d�|�n�\�ʉd�v��ʂʼnd�l��0�̃P�[�X���쐬���A�u�i���^�ϓ���p���̉d�P�[�X�v�Ń`�F�b�N�����Ă��������B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�R�X�D |
�Y��b�ɂ����āA�t�̉e�����l�������v�Z�͉\���B
|
| �`�P�|�R�X�D |
����P�Ƃʼnt�̌���������ꍇ�́A�u��b�|�n�w�f�[�^�v��ʂŒጸ�W��DE����͂�����A�u�l�����|����v�Z�v��ʂ̃��x��1�n�k���̉t�l���Łu�����A�l���̗����v��I�����Ă��������B
���x��2�n�k���̌����͖{���i�݂̂Ō������邱�Ƃ͂ł��܂���B
�u��b�̐v�E3D�z��(�����W���@�EH29�����Ή�)�v�Ƃ̘A�����K�v�ƂȂ�܂��B
|
| �@ |
|
| �p�P�|�S�O�D |
���̏d�v�x�iA��AB��j�̐ݒ�͉��ɉe�����邩�B
|
| �`�P�|�S�O�D |
�v�Z�ɂ͉e�������A�v�Z���̕\���݂̂ƂȂ�܂��B
���r����L2�n�k���̌����i�ۗL�ϗ͖@�ɂ��ƍ��j�ł́A�c���ψʂ̔�����s�����ǂ����ɉe�����܂����A�{���i�ł͒G�ǂۗ̕L�ϗ͖@�ɂ��ƍ��ɂ͑Ή����Ă���܂���B
|








