
|
|
|
「斜面の安定計算」は各種設計基準類にて規定される道路盛土、鉄道盛土、宅地造成等の各種土構造物・地すべり解析・防災対策・河川構造物の設計等に対応した斜面安定解析システムです。最新版においては、土構造物の性能設計への移行への対応として、ニューマーク法による動的解析機能の強化と港湾基準の「部分係数法による信頼性設計法レベル1での照査」機能に対応しました。
本製品最新版の主な改訂内容につきまして、事業主体の規定する性能設計との対応状況を含め以下にご紹介いたします。
●土工指針平成21年6月改定
道路土工要綱及び土工指針 切土工・斜面安定項指針平21年6月版が発刊され、性能規定型設計の考え方が土工指針としてはじめて取り入れられました。
改定指針においては、土工構造物の設計に際し、地震動の作用として「道路橋示方書V耐震設計編(平成14年3月)」に規定されるレベル1地震動及びレベル2地震動の2種類の地震動を想定することが規定されました。
◆道路土工(要綱、切土工・斜面安定工指針)の改訂とフォーラムエイトの対応
▼要求性能に対する作用力の規定
| 想定する作用 |
重要度 1 |
重要度 2 |
| 自重・交通荷重/降雨の作用 |
性能1 |
性能1 |
| 地震動の作用 レベル1地震動 |
性能1 |
性能1 |
| レベル2地震動 |
性能3 |
性能3 |
|
▼地震動の作用に対する解析法の規定
| 想定する作用 |
規定された照査方法 |
| 地震動の作用 レベル1地震動 |
円弧すべり安定解析や震度法等の静的解析法 |
| レベル2地震動 |
動的有限要素法やニューマーク法等の動的解析法 |
|
●NEXCO設計要領平成21年7月改定
NEXCO東日本は、平成21年7月1日付で技術基準類の改訂を行いました。
この改訂の中で「設計要領第一集 土工編」では、第6章として「高盛土・大規模盛土」が新規制定されました。その内容としては、ほぼ全般にわたりニューマーク法に関する規定であり、下図に示す高盛土及び大規模盛土に対して事実上ニューマーク法による動的変形解析が義務付けられる形となりました。
▼NEXCO設計要領 土工編 平成21年7月改訂における規定
| 計算種別 |
照査方法 |
| 常時 |
テンションクラックを考慮した修正フェレニウス法による単一すべり円弧を用いた全応力法 |
| 地震時 |
盛土条件や地形・地質等を考慮し、変位・変形量(残留変位量)を算出することを基本とする。
レベル2地震動に対する変位・変形量(残留変位量)は、すべり土塊の滑動変位量を対象とし、地震応答解析を用いたニューマーク法により算定することを基本とする。
但し、レベル1地震動に対する安定計算は、円弧すべり面を仮定した震度法により安定計算法を用いて良いものとする。 |
|
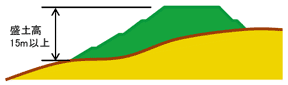 |
|
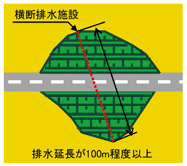 |
| ▲ニューマーク法の適用が義務づけられる高盛土の模式図 |
|
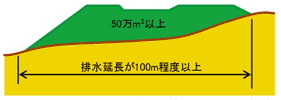 |
|
| ▲ニューマーク法の適用が義務づけられる大規模盛土の模式図 |
|
●本製品改訂と性能設計との位置づけ
我が国における性能設計の導入に起因するWTO/TBT協定では、設計の自由度を高めようとする動きであるのに対し、ISOやEurocodeは設計基準の統一化を進めようとするものといわれています。
この自由化と統一化という相矛盾するともいえる動向に対して、地盤コード21では、この自由化と統一化の動きに対処するために、照査アプローチAと照査アプローチBの2種類の照査アプローチを許容する形を採っています。
今回のVer.8における主な新機能として、アプローチAへの対応として地盤の塑性変形をある程度許容した土構造物の将来挙動予測が行えるニューマーク法による動的解析機能の強化を行い、アプローチBへの対応として港湾固有の設計コードで照査を行う「部分係数法による信頼性設計法レベル1での照査」の機能に対応しました。
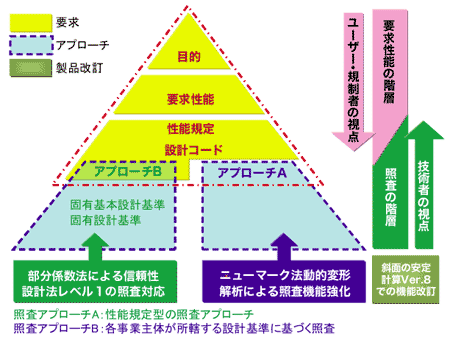
●新バージョン改訂機能
アプローチAはこの包括設計コードにしたがって、比較的自由に照査を行うアプローチを指します。これに対し、アプローチBは、包括設計コードにしたがって作成された固有設計コードで照査を行うアプローチになります。アプローチAでは、性能設計として長期的変位を設計に取り込むことが基本となり、盛土の塑性変形をある程度許容した土構造物の将来挙動予測が主流になると考えられます。一方、アプローチBの照査体系で推奨されているのが、港湾基準にて規定される部分係数法による信頼性設計法レベル1での照査という位置付けになります。
■照査アプローチA: ニューマーク法動的変形解析
ここでの性能設計の考え方は、地震荷重は一過性の現象であり、安全率が1を下回っても必ずしも壊滅的被害にならないとして、地震時の変形予測により変形を許容値以下に収めることを基本とした照査になります。
本年(平成21年)に入り、6月の土工指針の改訂による「道路土工として初めての性能照査型設計の導入」に引き続き、7月には、NEXCO東日本では技術基準類の改訂が行われ、ニューマーク法による動的変形解析の義務化が規定されました。これにより、これまでなかなか進捗が見られなかった土構造物に対する性能照査が、今後一気に加速化されていくものと考えられます。
本製品改訂では、ニューマーク法の耐震性能照査機能の強化を図ります。
| ◆アプローチAに対する最新バージョン改訂機能 |
| 1. |
対策工施工時のニューマーク法対応 |
| 2. |
地震動の方向考慮したニューマーク法解析に対応 |
| 3. |
降伏震度の直接入力によるニューマーク法計算に対応 |
| 4. |
ニューマーク法時刻歴図への降伏震度の描画に対応 |
| ◆アプローチBに対する最新バージョン改定機能 |
| 5. |
各種対象施設毎の部分係数のデータベースをプログラム内蔵 |
| 6. |
耐力の設計用値Rdが作用効果の設計用値Sdを上回るとした耐力作用比による破壊確率の照査機能 |
| 7. |
照査用残留水圧の計算 |
|
- 対策工施工時のニューマーク法対応
土構造物の性能照査では、ニューマーク法により未対策時現況解析を行ない、盛土の場合、良質な盛土材や抑制工による対策後解析により所要の要求性能を満足させます。一方、対象法面が切土の場合、抑止工による対策により対策後の残留変形解析の必要性が、対象法面が盛土の場合においてもジオテキスタイル等の補強盛土による対策後の残留変形解析の必要性が生じてきます。
今回の改訂では、下式で表される補強工による抵抗モーメントの項を新たに付加した円弧すべり土塊の運動方程式に対する線形加速度法により逐次計算に対応し、ニューマーク法による対策工の効果の性能評価が可能になります。
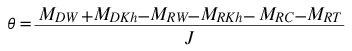 ここに、
ここに、
MDW :自重による滑動モーメント MRT :補強工による抵抗モーメント
MRW :自重による抵抗モーメント MDKh:地震時慣性力による抵抗モーメント(=Kh×MDk)
MRC :粘着力による滑動モーメント MRKh:地震時慣性力による抵抗モーメント(=-Kh×MRk)
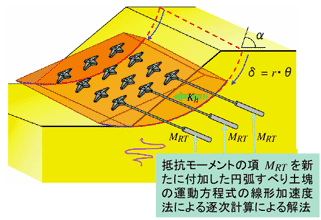 |
|
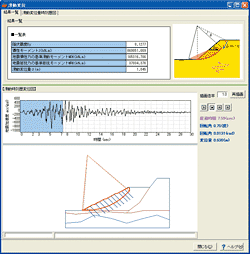 |
| ▲ニューマーク法による対策工効果の評価概念) |
|
▲ニューマーク法による対策工効果の性能評価 |
- 地震動の方向考慮したニューマーク法解析
地震動に伴う地盤の残留変位の規模は端的に強い地震加速度に対して大きくなるとは限らず、地震動の周期にも依存して地盤の変形が継続していきます。対象とする地盤の被害の大きさは、地震加速度の大きさのみに依存して決まるわけではなく、地震加速度の周期にも依存します。たとえ大きな地震加速度であっても、その振動数が高ければ1サイクルの時間が短くなるため、積分した変位は小さくなり、このような地震動は被害になり難いと言えます。そのため、発生する残留変位の照査に際しては、最大加速度の大きい方向のみでの照査のみでなく、地震加速度の方向を正負両方向の照査を行うことが望ましいと言えます。
本改訂より、入力地震加速度の方向を一定方向のみでなく、地震動が逆方向に作用した場合の解析も行う機能に対応します。これにより、耐震性能照査に際して両結果のうち、滑動変位量の大きい方を採用するとした照査が行えます。
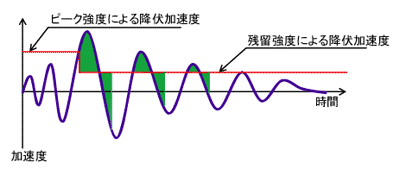
▲地震加速度を正方向と仮定した場合での地盤応答(現行バージョン)
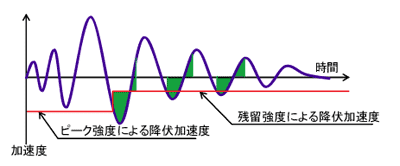
▲地震加速度を負方向と仮定した場合での地震応答(新バージョン)
- 降伏震度の直接入力
降伏震度Kyは安全率が1.0となる時の震度としてプログラムで自動計算しています。ここで、対象とする地盤の変形特性はその地盤の降伏震度に大きく依存し、降伏震度が大きくなるに従い変位量は小さくなることが考えられます。
本改定では、これまでの降伏震度の自動計算値による解析に加え、降伏震度の直接入力に対応します。これにより、対象とする円弧すべり面を固定した状態で降伏震度の値を任意に大きくすることにより、対象とする地震動に伴う変位量がどのように低減されるかの傾向を定量的に照査することが可能となります。
- 時刻歴図への降伏震度の描画
時刻暦図の出力に新たに震度を追加し、入力地震波形と降伏震度との関係を目視確認できるよう機能追加します。
■照査アプローチB: 港湾基準信頼性設計法レベル1対応
「港湾の施設の技術上の基準」が平成19年4月に改定され、性能のみが規定される性能規定に移行、構造物の要求性能の照査には、レベル1信頼性設計法である部分係数法が標準的な設計手法として用いられることになりました。
施設の破壊する確率がある許容値以下であることを、定量的に照査する設計手法が信頼性設計法であり、部分係数法は、特性値に部分係数を乗じて得られる設計用値を算出し、耐力の設計用値Rdが作用効果の設計用値Sdを上回ることを確認することによって性能を照査します。
本改訂では、港湾基準における信頼性設計法レベル1の部分係数法(地盤の支持力・地盤のすべり破壊)に対応しました。
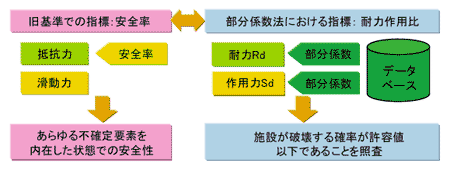
▲部分係数法による照査概念
|
斜面の安定計算セミナー
●日時 : 2009年 11月 11日(水) 9:30〜16:30 ●参加費 : \15,000 (1名様・税込 \15,750)
●本会場 : フォーラムエイト東京本社 GTタワーセミナールーム TV会議システムにて 東京・大阪・名古屋・福岡にて同時開催 |
■新土工指針対応 斜面の安定計算 Ver.8 リリース予定日:2009年9月 |
(Up&Coming '09 秋の号掲載) |
 |
|







>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス
>> ファイナンシャルサポート
|








