| SUPPORT TOPICS |
橋脚の設計のなぜ? 解決フォーラム |
保守・サポートサービス
関連情報 |
| UC-1 Series |
|
|
はりの形状は、全体の橋脚形状から設定しています。
また、設計時のはり形状は、柱形状が円形・小判形の場合には、柱幅の1/10を考慮した張出し長をセットします。
■許容応力度法の場合
<はりとして設計する場合>
鉛直方向のせん断力の照査位置は、「はり付け根高さの1/2より先端側の支承位置」および「はり付け根高さの1/2」の位置としています。
水平方向のせん断力の照査位置は、「上部工支承位置」および「はり付け根」としています。
<コーベルとして設計する場合>
鉛直方向のせん断力の照査位置は、「考え方」−「許容応力度法」−「はり」−「せん断照査位置」の設定に従います。
・はり高さの1/2位置および1/2より先端側の支承位置を選択した場合:通常のはりとしての照査と同じ位置とします。
・全ての照査位置とした場合:全て(はり高さの1/2位置より内側の支承位置含む)の支承位置について照査します。
■保有耐力法の場合
水平方向のせん断力の照査位置は、「上部工支承位置」および「はり付け根」としています。
|
Page Top 
|
| SUPPORT TOPICS |
VRのなぜ? 解決フォーラム |
保守・サポートサービス関連情報 |
| UC-win/Road |
|
|
前号では、データ作成時のモデル、テクスチャでの工夫について紹介致しました。今号は、Road上の設定でパフォーマンスを向上させる方法について紹介致します。
1.描画オプション
- 画面表示タブで不要な項目を非表示にする(特に、湖沼はFPSに大きく影響します。)
- 運転時にミラーを考慮しない場合は、左右のサイドミラーとバックミラーのチェックを外す。
- 地形タブの「視野半径」の距離を小さくする。最小値は500mです。
- パフォーマンスタブの「Visibility Angle」の数値を上げる。
- パフォーマンスタブの「オクルージョンカリング」を設定する。
(OpenGLの拡張命令「GL_HP_occlusion_test」をサポートしたビデオカードが必要です。)
- その他タブの画角を無駄に広くしない。
2.地形
- 地形パッチを利用している場合、標高点の数を少なくする。
3.シミュレーション
- [オプション]-[景観のモデル表示]で、走行範囲外のモデル、樹木、標識など非表示にした景観を作成し、シミュレーション時に切り替える。可能なものは極力切り分けて表示させる。
- MD3、3D樹木などの数は必要最低限にする。走行車両も台数を極端に多くしない。
- 景観ビュー、3面表示などはパフォーマンス低下となります。
4.その他
- 読み込みデータを開いたら、作成範囲を一通り回って全部のモデルを読み込んでからデータを動かし始めます。
(最初にモデルを表示する際は初期読み込みに時間がかかるため)Ver3.4以降なら初期設定で設定も可能です。
- 線形やモデルの重複配置はFPS低下の原因になるため、極力避けるようにします。
以上、2号に渡りパフォーマンス向上の方法を紹介致しました。データの工夫やUC-win/Roadの設定によってより良いパフォーマンスで、VRのプレゼン、ドライブシミュレーションを行っていただければと考えます。
|
Page Top 
|
|
|
|
斜橋,曲線橋などでは1方向に加震しても、橋脚の主軸の傾きおよび上部構造の剛性などにより、橋脚は二軸曲げを受けることがあります。このような構造物に対して一軸曲げを想定したM-φ要素では実現象と異なる結果となる可能性があります。このような場合、二軸曲げを自動的に考慮することができるファイバー要素の適用がふさわしいと考えられています。しかし,ファイバー要素でモデル化した場合には、照査方法が難しいということもあります。今回は、検討事項をご紹介します。
1) ひずみによる照査
断面内のセルに生じたひずみ値で損傷度を判定することで照査とすることが考えられます。UC-win/FRAME(3D)には、ひずみで判定する損傷基準を設定することができるので、この機能により応答値を色で識別することができます。終局Iや終局IIは道路橋示方書V耐震設計編(以下、「道示V」と略します)が想定する設計上の限界値ではなく,あくまでも部材の終局状態(プログラムでは終局I,IIという損傷基準名で表示しています)を指しています。したがって、道示Vに解説されている許容塑性率や許容曲率に相当する"許容ひずみ"で判定することが理想的です。ところが、道示Vにはそれが示されていません。終局ひずみに対してどの程度の安全率を考慮して許容ひずみを設定すればよいかは,設計者の判断となります。
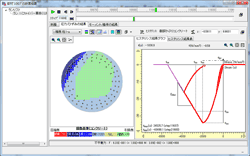 |
| ▲ひずみ分布の例 |
2) 曲率による照査
ファイバー要素に生じた応答曲率をM-φ特性から算出した許容曲率で照査する方法があります。この方法は、部材レベルでの照査という意味では、道示Vに準じていますので、UC-win/FRAME(3D)ではこの方法もサポートしています。ただし、この場合、フレーム計算時は軸力変動を自動的に考慮した応答曲率、許容曲率は本体解析前に予備計算で求めた軸力に対する許容曲率となりますので、軸力変動の影響が無視できない構造物については,両者の軸力の仮定が不整合となりますので完全ではありません。
3) 平均弾性剛性残存率による照査
2002年制定のコンクリート標準示方書【耐震性能照査編】p.88を参照すると,ファイバー要素の解析事例としてコンクリートの平均弾性剛性残存率を用いて照査されています。ただし、本プログラムにはこれを自動的に行う機能がありませんので、セルに生じた応答ひずみをご自身で整理していただく必要があります。二軸曲げの影響が小さいと考えられる場合は、一軸曲げ問題としてM-φ要素やM-θモデルでモデル化することができます。照査もUC-win/FRAME(3D)が搭載している許容曲率の照査やばね要素の回転角照査の機能が利用できます。ただし,この場合も軸力変動の影響が小さいとみなせる場合に限定されます。軸力の時刻歴結果を確認して判断することになります。
ファイバー要素でモデル化すれば、解析自体は二軸曲げや軸力変動の影響を適切に考慮した解が得られます。照査には検討が必要ですが、ファイバー要素を用いることでより精度の高い解析が可能です。是非ご利用ください。 |
|








