| Q3-1. |
抵抗モーメントの算出方法
上下フランジの抵抗モーメントの算出方法を教えて下さい。 |
| A3-1. |
一般的には、MR=σa×I/yで表示される抵抗モーメントですが、本プログラムの場合は、せん断応力度や合成応力度で決定される事を想定して以下の方法により算出しています。
着目点の内、曲げ,せん断,合成応力度の最大値となる箇所を選択し、許容値との比率を求めます。

曲げ応力度の比率=σa/σ
せん断応力度の比率=τa/τ
合成応力度の比率=1.2/合成応力度
比率の小さくなるケースを用いて設計曲げモーメントに乗じ、抵抗モーメントとしています。
抵抗モーメント=設計曲げモーメント×最小比率
つまり、言いかえれば「応力度の余裕」とも言えます。 |
| |
|
| Q3-2. |
詳細設定リブオプションについて
[f8:処理]の詳細寸法入力項目に「リブオプション=1」がありますが、これはどんな働きをするのですか? |
| A3-2. |
有効幅を考慮した断面計算を行った時、リブ幅がフランジ有効幅境のどこまで入っているかで、そのリブ断面が有効か否かの判断をします。
[リブオプション=0] は、リブ幅の1/2以上が有効内に入ってれば一本と計上する。
[リブオプション=1] は、リブ幅の全てが有効内に入ってれば一本と計上する。
という機能です。
〔 例 〕
腹板実間隔 = 2500
リブ形式 = Uリブ
リブ寸法 = 300×220×6
リブ本数 = 4本
下図の様にリブが配置される。
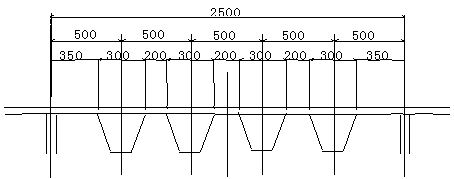
中の2本のリブ幅に有効幅が、かかるかどうか考えると、
リブオプション=0の時
有効間隔 = 2000以上入力の時 → 4本全て有効。
〃 = 2000未満入力の時 → 中2本無有効。外2本有効。
リブオプション=1の時
有効間隔 = 2300以上入力の時 → 4本全て有効。
〃 = 2300未満入力の時 → 中2本無有効。外2本有効。
となります。 |
| |
|
| Q3-3. |
詳細設定「面外全幅有効」と「せん断全幅」について
[f8:処理]の詳細寸法入力項目に「面外全幅有効 = 1」と「せん断全幅 = 1」がありますが、これはどんな働きをするのですか? |
| A3-3. |
- 面外全幅有効
上下フランジに有効幅が考慮されている断面に、面外曲げモーメントが作用した時、面外曲げモーメントによる実応力算出時に上下フランジの有効幅を考慮した断面で計算するのか(これが0)それとも、有効幅が入力されていても全断面有効で計算するのか(これが1)を指示します。
図化すると、
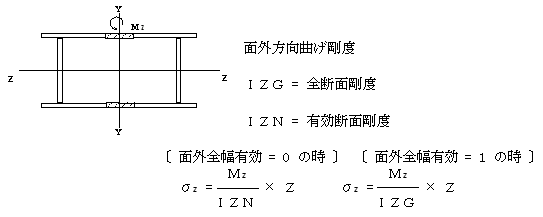
- せん断全幅有効
上下フランジに有効幅が考慮されている断面で、せん断流によりせん断応力度を算出する際、有効幅外の範囲を無視してせん断流を算出するか(これが0)それとも有効幅が入力されていても全断面有効幅で計算するか(これが1)を指示します。

|
| |
|
| Q3-4. |
「軸力+」と「軸力-」の入力方法について
[f8:処理]の詳細寸法入力項目に「合計軸力+」と「合計軸力-」がありますが、この意味と入力方法を教えて下さい。 |
| A3-4. |
断面計算に対し、軸力最大時と最小時とを同時に計算させるために分かれています。
「合計軸力+」は、曲げによる応力度の+側(引張側)に加算する軸力。
「合計軸力-」は、曲げによる応力度の-側(圧縮側)に加算する軸力。
を示します。いずれも引張軸力を正、圧縮軸力を負の符号で入力します。
仮に、軸力最大最小時が無くひとつの軸力値であれば両者に同じ値を入力してもかまいません。
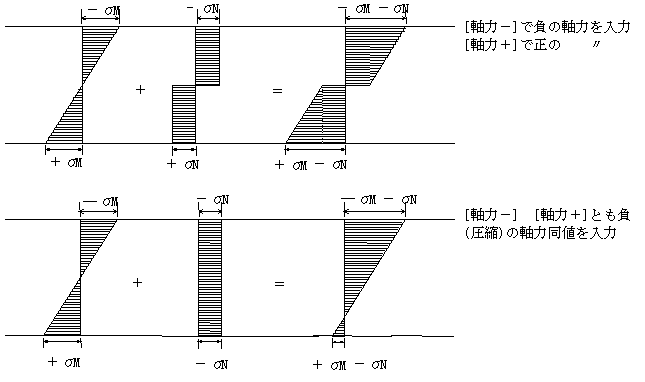
|
| |
|
| Q3-5. |
Uリブ形状寸法の入力方法
Uリブを入力したいのですが「上リブの寸法間違い」と表示されて計算しません。どのような入力方法ですか?また、任意なリブを使用する方法はありますか? |
| A3-5. |
上リブ寸法にUリブを入力する時は、Uリブの高さと厚さで入力します。
例えば、U-320*240*6を入力する場合は、【24006.0】と入力します。
U-300×220×6 → 【22006.0】 と入力。
U-300×220×8 → 【22008.0】 と入力。
U-320×240×6 → 【24006.0】 と入力。
U-320×240×8 → 【24008.0】 と入力。
U-320×260×6 → 【26006.0】 と入力。
U-320×260×8 → 【26008.0】 と入力。
鋼床版箱桁断面計算用の上リブ定義ファイル[RIB.DEF]があります。
プログラム領域の【\MB\DEF】の中に出荷時のファイルがありますので、任意に追加して使用できます。
|
| |
|
| Q3-6. |
フランジ腹版位置のねじりせん断τMT=0の理由
応力度表のせん断応力で、UFLG腹板点のねじりによるせん断応力度が「0」となっている箇所があります。ねじりモーメントを入力していますので「0」ではおかしいのではないのでしょうか?
| kgf/㎝2 |
σN σM Σσ σa |
τS τMT τΣ τa |
合成応力度 |
| UFLG左端 |
0-1283=-1283<2100 |
0= 0<1200 |
0.37<1.2 |
| UFLG左腹 |
0-1327=-1327<2100 |
166+ 56= 222<1200 |
0.43<1.2 |
| UFLG右腹 |
0-1393=-1393<2100 |
212+ 0= 212<1200 |
0.47<1.2 |
| UFLG右端 |
0-1450=-1450<2100 |
0+ 0= 0<1200 |
0.48<1.2 |
| WEB 上縁R |
0-1380=-1380<2100 |
430+ 75= 505<1200 |
0.61<1.2 |
| WEB 中央R |
0+ 0 = 0<2100 |
481+ 75= 556<1200 |
0.22<1.2 |
| WEB 下縁 |
0+1936= 1936<2100 |
366+ 75= 441<1200 |
0.98<1.2 |
| LFLG左端 |
0+1966= 1966<2100 |
0+ 0= 0<1200 |
0.88<1.2 |
| LFLG左腹 |
0+1966= 1966<2100 |
111+ 25= 136<1200 |
0.89<1.2 |
| LFLG右腹 |
0+1966= 1966<2100 |
115+ 25= 140<1200 |
0.89<1.2 |
| LFLG右端 |
0+1966= 1966<2100 |
0+ 0= 0<1200 |
0.88<1.2 |
|
| A3-6. |
上フランジは腹板点には、箱内からのせん断応力度と箱の外(張出部)からのせん断応力度が集まって来ますが、本プログラムではどちらか大きくなる方のみを一行で表示するものとしています。
張出部側はτSのみであり、箱内側からはτSとねじりモーメントによるせん断応力度τMTがありますので、
箱内(τS+τMT)と張出部(τS)との大きい方
を印字しています。つまり、張出部の張出長が大きい時ほど、箱の外の せん断応力が大きくなり、箱内のτs+τMTより大きなる場合があります。その場合にτsには張出部かのせん断応力度そのものの値を印字し、当然張出部ですのでねじりによるせん断応力度はありませんから(τMT=0)と印字します。
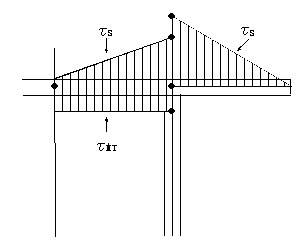
|
| |
|
| Q3-7. |
鋼床版断面計算での「箱中心から図心位置までの距離(DZ、DY)」の取り扱い |
| A3-7. |
・Z軸は腹板間隔の中央位置にあり下向きを正
・Y軸左右腹板高平均の1/2位置にあり右向きを正
としており、
DZ: Z軸方向の距離
DY: Y軸方向の距離
としています。 |








