| Q6-1. |
ファイル名の入力
プログラムを起動すると「ファイル名入力」となりますが、なにを入力しても「断面ファイルが在りません」と表示され先へ進みません。どのように使用するのですか? |
| A6-1. |
『断面計算、幾何学計算』での作業選択画面で、【5】柱トラスアーチ部材の断面計算と【8】柱トラスアーチ部材の継手計算はペアで使用します。
まず、【5】で断面計算を行い[f6:セーブ]を押してデータを保存します。その後、【8】を起動して「ファイル名の入力」の時に【5】の断面計算で保存し作成したファイル名を入力します。これにより、保存ファイル内には断形状寸法や実応力度等がありますので、それらのデータが継手計算に引き継ぎがされて利用されることになります。
つまり、【5】の断面計算を行わずに【8】を起動すると【5】で作っておかなければならないファイルが無いので「ファイルが在りません」と出ます。 |
| |
|
| Q6-2. |
縁端寸法1と2の入力
「フランジ定義」の中に「縁端寸法1」と「縁端寸法2」という入力項目がありますが、これはどこの寸法で、どのような結果に影響してくるのか教えて下さい。 |
| A6-2. |
面外方向の曲げモーメントが作用した時、面外モーメントにより生ずる応力を上下フランジが負担する範囲を入力するのが縁端寸法です。
フランジ端に着目して腹板間隔中心に向かって入力し、
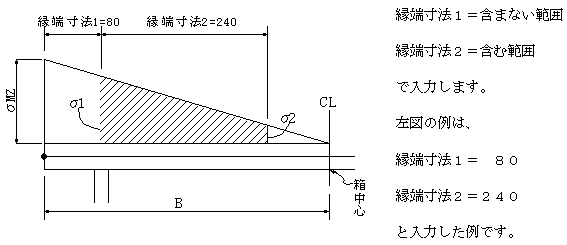
ゆえに面外応力によりフランジに作用する応力は、σ=(σ1+σ2)/2となります。 |
| |
|
| Q6-3. |
計算結果で設計応力度は実応力度のn倍する
出力中「設計応力度は実応力度をn倍した応力度を用いる」とありますが、この方法の根拠とn値の算出方法について教えて下さい。 |
| A6-3. |
雑誌『道路 1975-11』の連結に関する示方書小委員会による記述(P65~P66)[質問17]解答(2)記される。「二軸の曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の継手の設計応力度」に準じて設計しています。次のページの出力例について係数の算出は下記のとおりです。
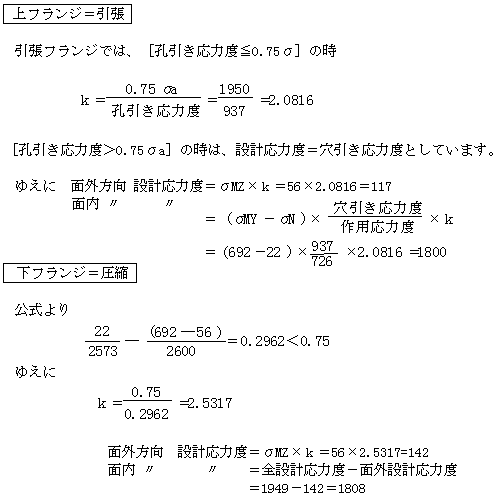 |








