| Q10-1. |
腹板有効幅算出式の根拠
印字内容項目中、腹板有効幅の算出式として
腹板有効幅=補剛材断面積×0.7/腹板厚
とありますが、この0.7の意味を教えて下さい。 |
| A10-1. |
道示Ⅱ-8.7 及び、鋼道路橋設計便覧に従い計算しています。
[有効幅 1]道示Ⅱ-8.7.1より腹板厚の24倍の範囲。
[有効幅 2]設計便覧により、全断面積は補剛材断面積の1.7倍以下とする。
補剛材断面積をAとすると、腹板有効幅は、
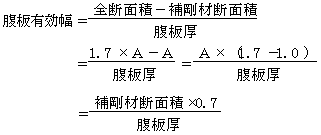
以上[有効幅 1]と[有効幅 2]の小さくなる値を比較して採用していますが、上記の有効幅
2の算出式を示しています。 |
| |
|
| Q10-2. |
支点上補剛材の出力の手計算(1)
次の出力例をもとに、手計算で追って解説して下さい。特に、有効幅の算出式の根拠を教えて下さい。 |
| A10-2. |
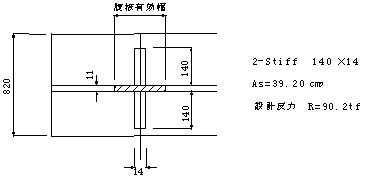
1)腹板有効幅の照査
・腹板断面積=12t×2×t=12×1.1×2×1.1=29.04c㎡
(道示Ⅱ-8.7.1)
・総有効断面積=29.04+39.02=68.24c㎡>39.20×1.7=66.64c㎡
・ゆえに腹板有効幅は
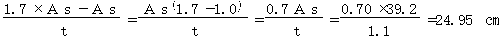
2)断面諸量
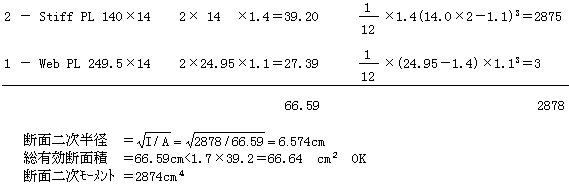
3)補剛材板厚の照査
最小補剛材幅は道示Ⅱ-5.8.2の(2)より腹板高の1/30に50㎜を加えた値以上とする。
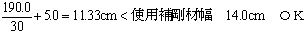
最小補剛材厚は、同じくⅡ-1.8.2の(4)に補剛材の1/13以上とありますが、より危険例を考えて本プログラムではⅡ-3.2.2(2)表-3.2.3より、自由突出板の局部座屈に対する許容応力度を採用しています。SS41相当で、
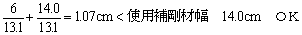
4)応力度の照査
許容応力度はⅡ-2.2.1の表-2.2.2より局部座屈を考慮しない許容軸方向圧縮応力度より求める。
有効座屈長は、Ⅱ-8.7.1(2)よりけた高の1/2とする。ゆえに、
l=Hw/2=190/2=95 ㎝
l/r=95/6.57=14.46≦20
ゆえに σa=1400kgf/c㎡とする
実応力度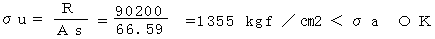
5)溶接の検討
反力による必要脚長は、τa=800kgf/c㎡として逆算する。
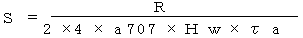
板厚による必要脚長は、道示Ⅱ-4.2.4(2)より、
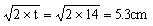
以上より、腹板と補剛材の隅肉溶接脚長を 6㎜とする。 |
| |
|
| Q10-3. |
中間補剛材の手計算(1)
次の出力例をもとに、手計算で追って解説して下さい。 |
| A10-3.
|
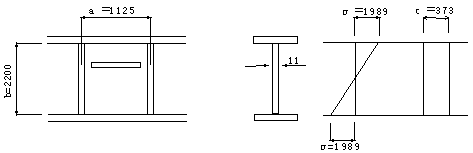
[垂直剛材の設計]
1. 補剛材間隔の照査(道示Ⅱ-8.5.1)
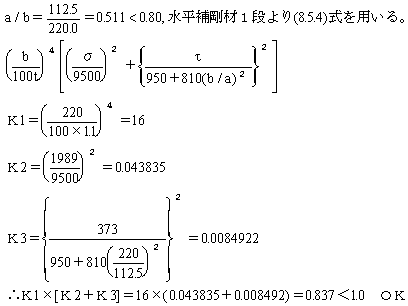
2. 垂直補剛材断面の照査(道示Ⅱ-8.5.2より)
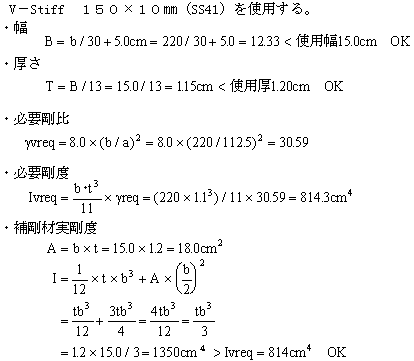
[水平補剛材の設計]
1.腹板厚の照査(道示Ⅱ-8.4)
水平補剛材1段、腹板材質2100相当より最小腹板厚はb/209とする。
尚、計算応力度と許容応力度の比より
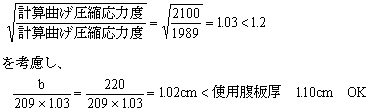
2. 水平補剛材断面の照査(道示Ⅱ-8.6.2)
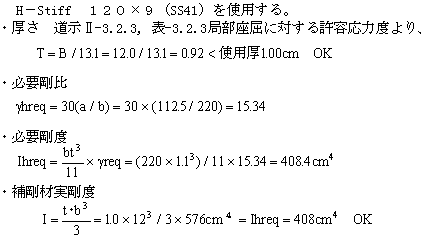 |
| |
|
| Q10-4. |
スタッド 計算結果で端支点上主荷重=0となる理由
出力内容のうち、「スタッド間隔」表の中で、支点上の死荷重による水平せん断力の値が「0」となるのは何故でしょうか? |
| A10-4. |
スタッドの設計に用いる水平力の組合せは道示Ⅱ-9.5.2にあるように、
1.合成後死荷重十温度差 → 支間部より支点部へ向う水平力
2.乾燥十温度差 → 支点部より支間部へ向かう水平力
のいずれかの水平力の大きくなる場合について設計します。
この判断をプログラムが行っているため、支点上で支間から支点への水平力の合計が458、逆に支点から支間への水平力の合計が465と二次応力の方が大きくなったためその値を使っています。通常は、支間部から支点部への水平力の方が大きくなるものですが、今回入力された条件では、以上のような結果になります。
詳細は、示方書、及設計便覧の計算例を参照して下さい。
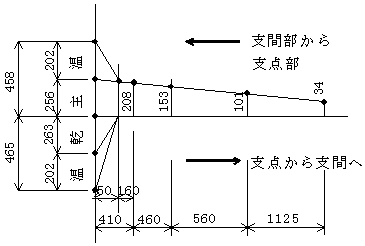 |
| |
|
| Q10-5. |
乾燥収縮軸力と温度差軸力の入力値の計算方法
「乾燥収縮軸力」と「温度差軸力」に入力する値の計算方法を教えて下さい。 |
| A10-5. |
1)[温度差軸力(kgf)][NT=ΣQT]
温度差による水平力(ΣQT)を kgf単位で入力します。
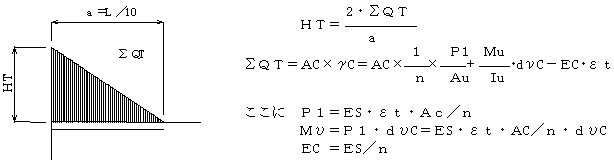 |
| |
|
| Q10-6. |
支点上補剛材の許容軸方向圧縮応力度の算定
応力度照査での許容応力度は、どの様に算出しているのですか? |
| A10-6. |
支点上補剛材の許容軸方向圧縮応力度は、道示Ⅱ-2.2.1により算出しています。また、8.7.1により有効座屈長は腹板高の1/2としています。次のページの出力例では、
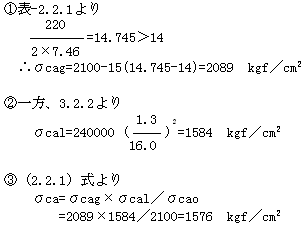
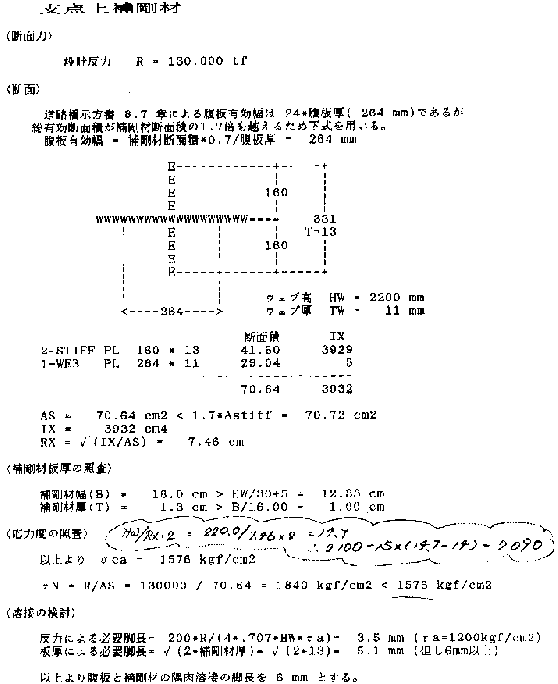 |
| |
|
| Q10-7. |
必要脚長の算出
支点上補剛材の設計で、印字すると反力による必要脚長が出力されますがその算出式を教えて下さい。 |
| A10-7. |
まずは、単位をkgfとcmで手計算してみます。
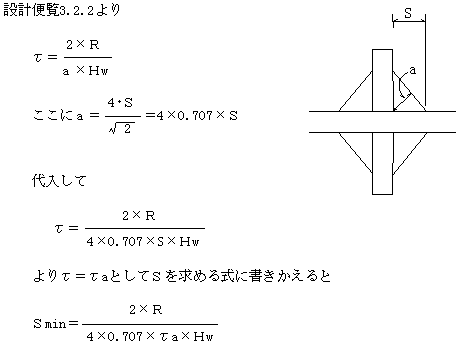
各項のうち、反力(R)は[ton]で、腹板高(Hw)は【m】で扱っているため、分子に1000/100=10倍とし、尚かつ算出される結果がcm単位なのでそれをmm単位にするため、更に10倍、合計100倍されています。
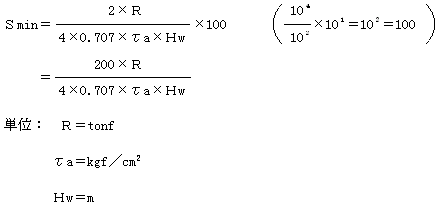 |








