| Q17-1. |
単純桁支間中央の最大モーメント発生位置の印字
断面力プリンタ出力で印字しましたが、単純桁で支間中央に横桁があるにも関わらず支間部モーメントの最大位置が支間部中央になっていません。何か原因はありますか? |
| A17-1. |
結論から申しまして、本プログラムが算出しているMmax位置は、M曲線の補間によって求まるMmax位置を示しており、格子解析上、横桁分配の影響によってモーメント図を極端に描くと、
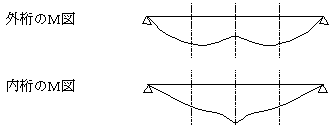
の様になります。次のページの様な位置のMmaxを算出しています。
[外桁]
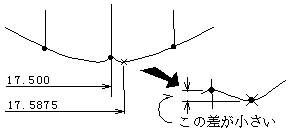
[断面力]
G1
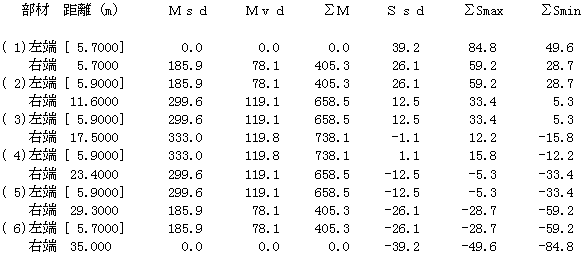
支間部モーメントの最大値
1径間目 差支点からの距離 = 17.5875m
M=
738.1 tfm S= 15.5 tf
この  は、主桁の剛度(外桁と内桁の剛度の差が大きい程 は、主桁の剛度(外桁と内桁の剛度の差が大きい程 が大きくなる。) が大きくなる。)
横桁の剛度のバランスによっての差が大きくなりますが、たまたま小さい山になっていて、最大位置が中心とほとんど変わらないため、同じ値として印字されています。例えば、極端に横桁が強かったりすると、もっと顕著にこの現象が見られると思います。
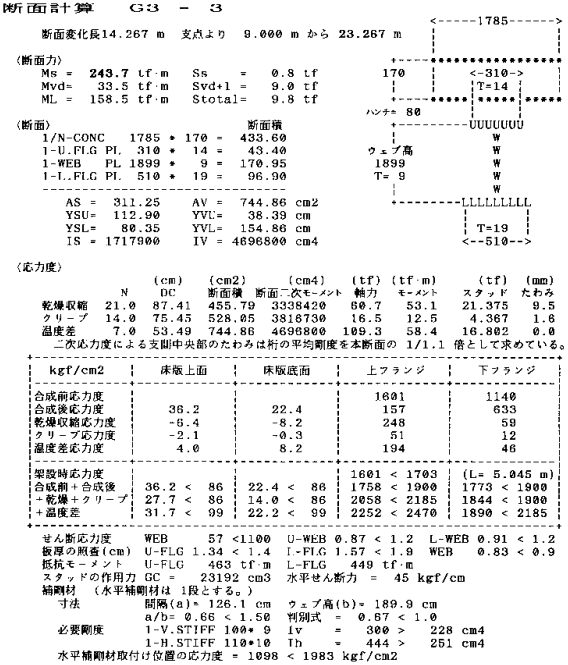 |
| |
|
| Q17-2. |
任意点の腹板高の算出(補間)方法。
単純桁で、たいこ橋の設計を行いますが、任意点の腹板高はどの様な補間式で算出しているのですか? |
| A17-2. |
腹板高変化形式=1(一定もしくは線形内)と指示し、腹板高の編集で、横断線毎に異なった腹板高を入力すると、腹板下縁(もしくは上縁)を水平に仮定し、上縁側に3次補間曲線を設定して入力値の腹板高を算出します。
[例]
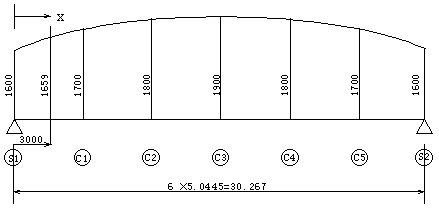
算出位置より、前後4格点を通る3次補間曲線(ラグランジェ)を設定して、指示位置の腹板高を算出する。
[X=3.0m位置]
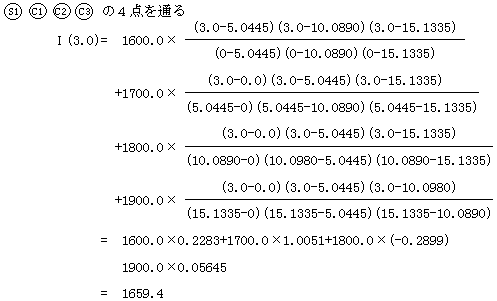 |
| |
|
| Q17-3. |
箱桁腹板高変化の入力方法
箱桁中心で腹板高一定とし、上フ ランジが横断線毎に変化する場合
の腹板高設定方法を教えて下さい。
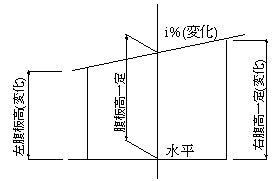
|
| A17-3. |
その方法を説明する前に理解しておかなければならない事は、高さの基準となる左右腹板及び中心ラインのハンチ下面標高が正しく入力されているかです。
線形計算によって算出されている各ラインの路面標高から、入力した舗装厚床版厚ハンチ高を引いた標高が左右腹板高を算出するための基準標高になります。線形登録において、上フランジが水平になる様に左右ハンチ高を入力している場合は意味がありません。
- STEP1 : 断面力登録の主桁設計の為の初期設定で、
- 【腹板高変化形式】=3:腹板幅中央を2次式
【標 準 腹 板 高】 =腹板中央での腹板高を入力する
【腹板高変化形式】=1(どちらでもよいが一応1の下側)
- STEP2 : 主桁設計の為のデータ、断面力の編集の腹板高の編集をひらくと主桁番号を聞いてきます。まずは1としてリターン
- STEP3 : 腹板高計算式の算出画面となりますが1つ目の1行に以下を入力します。
- 【 種 類 】=0:一定
【区 間 長 】=概当する桁番号の全部材長(断面力プリンタ出力を参考にする。)をm単位で入力。
- STEP4:【f1 : 次 作 業】を押すと、その桁の計算を行う。次の桁へ進むためSTEP2へ戻る。
|
| |
|
| Q17-4. |
曲線桁の設定方法
曲線I桁の自動設計で行う場合の注意点について |
| A17-4. |
曲線桁に関する点についてまとめます。
STEP1:線形計算プログラムで曲線としての線形計算を行い結果ファイルを作用しておきます。
STEP2:自動設計線形登録にて初期設定入力後、線形計算結果ファイルを読み込みます。
STEP3:線形の性質の「ラインが曲線かを入力」にて曲線桁のラインに【2:曲線】を指定します。
STEP4:「変形法=主桁のセクションの入力」にて、全ての横断線に剛度部材を入力するため【2】を入力します。
これは、曲線桁のため全ての横断線に主桁のねじれを防止するための横桁部材が必要となるためです。
尚、両端支点上セクションは、必要という訳ではありませんので任意に指定して下さい。また、実際の横桁部材の剛度は、一旦作成されたUC-GRID入力データファイル【.UCG】の中身をエディタで直接修正して下さい。
STEP5:残りの入力を行い、「線形ファイル出力」後、「面外変形法データ作成」でUC-GRID用入力データファイル.UCGを作成します。作成後、GRID実行のためMBを終了しMSDOSへ戻します。
STEP6:エディタで【.UCG】を確認修正し、格子計算を実行します。終了後、MB取込用断面力ファイル【.GRL】保存領域からデータ領域へコピーします。
STEP7:MBを起動し、「断面力登録」を選択します。
『主桁初期設定』の「主桁設計の為の初期設定」で【I桁の曲線桁計算方法】を指定します。
0:全ての直線桁
1:曲線桁で、上下に横構あり
2:曲線桁で、下にだけ横構あり
このスイッチと、次に入力する「曲線桁の半径の設定」での数値の関係は、下表となります。
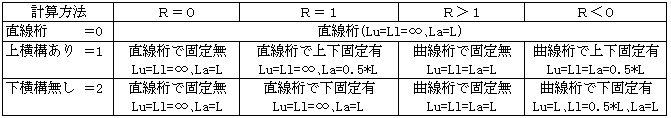
STEP8:『主桁設計の為のデータ、断面力の編集』の一番最初の「腹番高床版幅ハンチ高半径の自動設定」を実行します。
このメニューを実行することで、線形情報より全桁全横桁区間毎の曲率を内部計算し、次の「曲線桁の半径の設定」
STEP9:「曲線桁の半径の設定」画面で実際の半径を入力します。自動設定された細い値が入っていますが、必要であれば丸い値等に修正して下さい。この時、入力する値がR=0,R=1,R>1,R<0によって固定点の取り方がわかります。詳細はマニュアル自動設計P-66を参照して下さい。
以上、途中曲線桁に関係しない画面の説明は飛ばしましたが必ず順番に入力して下さい。 |








