| Q18-1. |
M/Megの考慮=1
画面の中で、「曲げ圧縮許容応力度【M/Meq】考慮=1」という項目がありますが、どの様な働きがあるのですか? |
| A18-1. |
[曲げ圧縮許容応力度でM/Meq考慮→0しない]
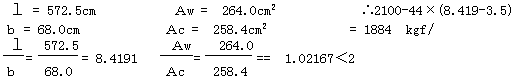
[曲げ圧力許容応力度でM/Meq考慮→1する]
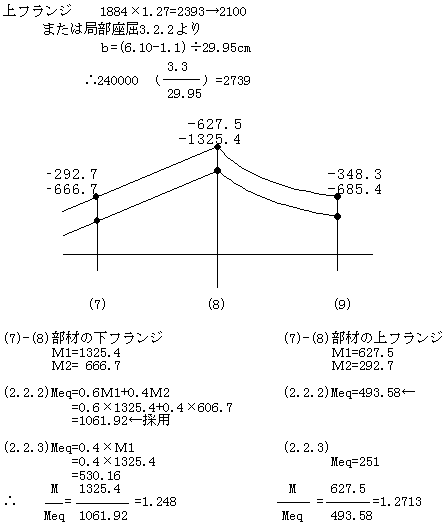
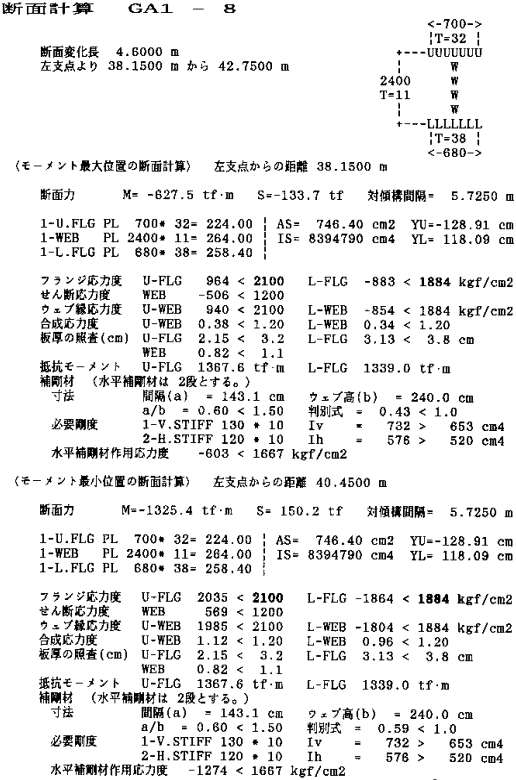
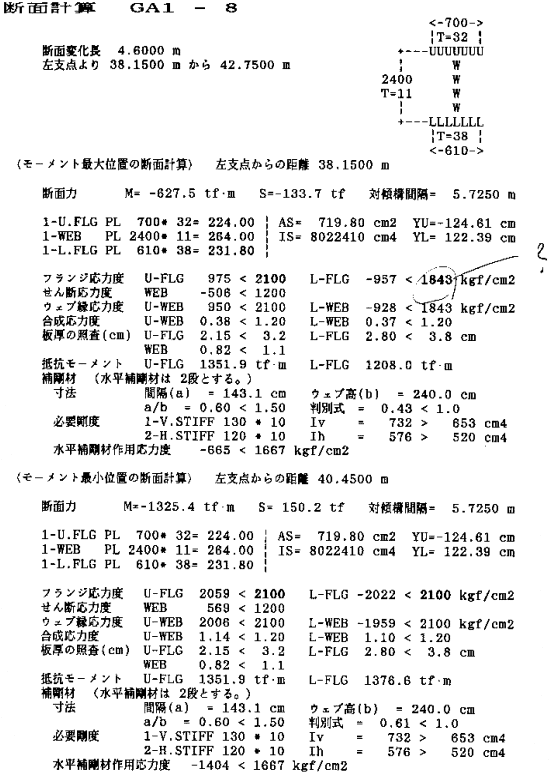 |
| |
|
| Q18-2. |
曲率不可応力の算出
曲率による不加応力を考慮していますが、例を挙げて算出方法を解説して下さい。 |
| A18-2. |
次のページの出力例について計算します。
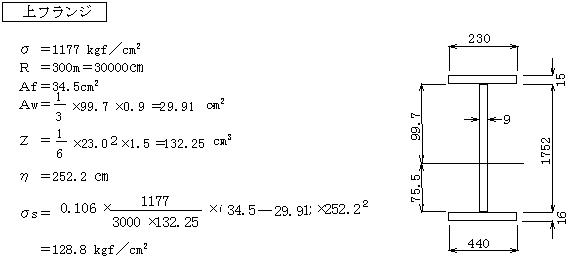
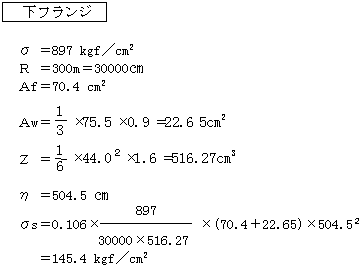
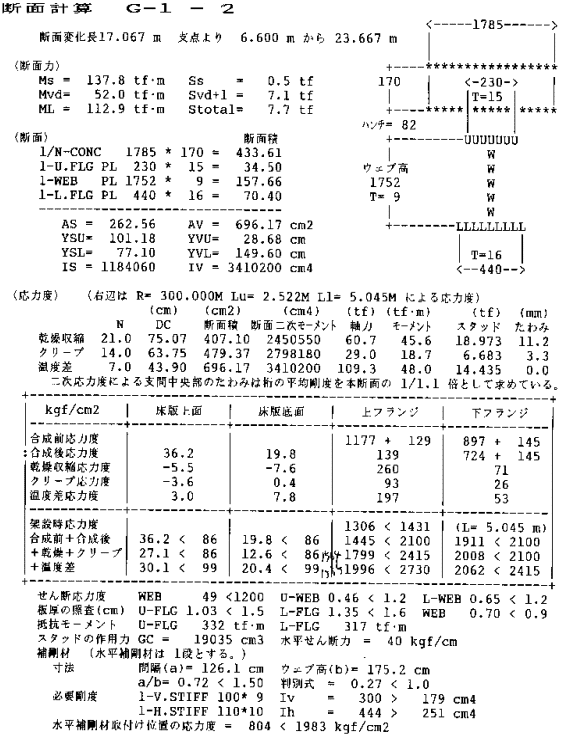
|
| |
|
| Q18-3. |
必要板厚の算出
印字項目中、上下フランジ腹板の必要板厚の算出方法を教えて下さい。 |
| A18-3. |
次のページの出力例を表に解説します。
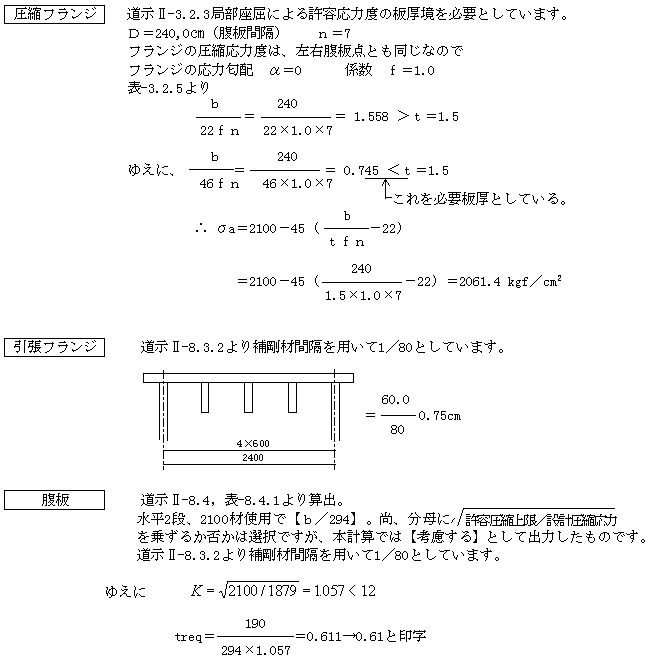

|
| |
|
| Q18-4. |
合成桁降伏点応力度
降伏点応力度は算出しないのですか? |
| A18-4. |
降伏点応力度の算出は、断面計算とプリンタ出力画面上、印字モードを[4]にして出力して下さい。
[合成前]
上フランジσ=860×1.3=1048
下フランジσ=801×1.3=1041
[合成後]
死荷重分比率 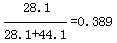
活荷重分比率 1-0.389=0.611
上フランジσ= 39×(0.389×1.3+0.611×2)=
67
下フランジσ=583×(0.389×1.3+0.611×2)=1007
[ 集計 ]
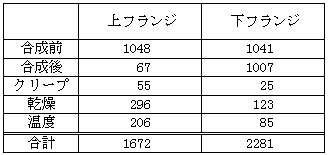
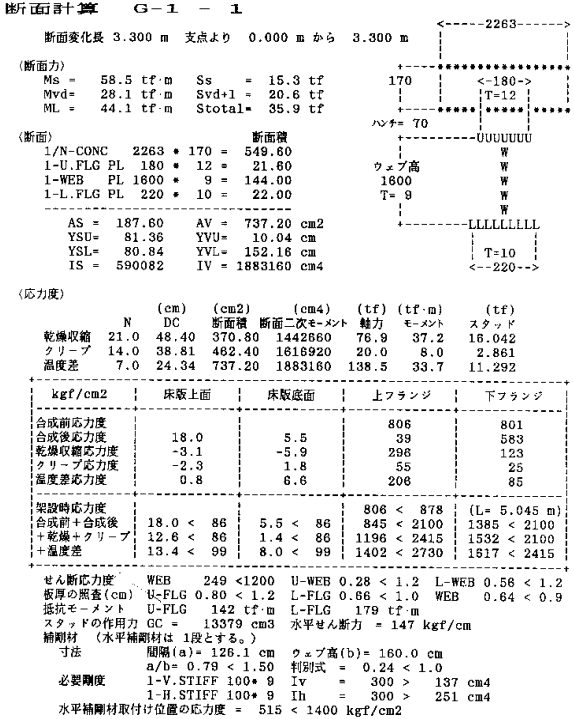 |
| |
|
| Q18-6. |
箱桁リブ本数の入力
箱桁自動設計で、リブ本数の入力について教えて下さい。 |
| A18-6. |
まずは、『断面計算の初期設定』で「上下のリブ本数が断面で一定=0、横桁間隔で一定」の入力によりリブ本数の入力を断面変化毎に行うか、横桁区間毎に行うかを選択します。
[断面毎に一定=0の時]
『断面毎に設定するデータを入力』の「【10】データの編集」の画面を桁番号毎に開き、[f9:次項目]を押して横画面2目を表示すると上リブ数,下リブ数の入力項目が現れます。ここで、入力します。
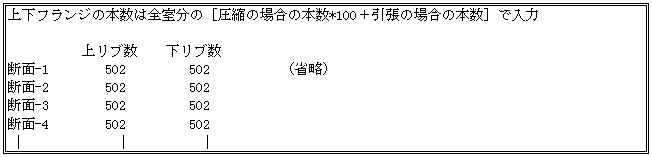
[横桁毎で一定=1の時]
『基本寸法と区間毎に設定するデータの入力』の「【11】データの桁毎の編集」の画面を桁番号毎に開き上リブ数,下リブ数の入力項目に入力します。
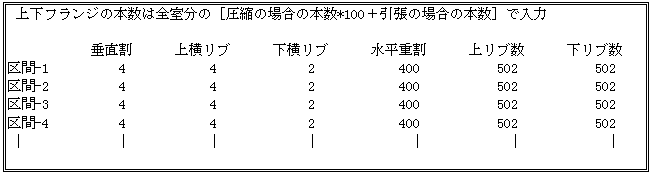
【本数の入力方法について】
上記までは、断面毎か横桁間毎かの入力について説明しましたが、実際の値の入力方法について説明します。
この内容は、断面毎でも横桁毎でも同じ考えです。
①横項目の[上リブ数]は上フランジ、[下リブ数]は下フランジに付くリブ本数を示します。縦項目には、起点側から断面変化毎もしくは、横桁区間毎に順番がついて表示されます。
②初期値としては「断面変化長等のデータの自動作成」で、標準リブ間隔により内部計算された本数が表示されてきますので、確認し必要であれば手修正します。
③値の入力は、単純に本数だけを入力するのではなくて「着目する断面変化もしくは横桁区間のフランジが、もし圧縮だったら何本かを百の位に、もし引張だったら何本かを一の位に数値として入力します。」
例えば、圧縮の時5本、引張の時2本としたら【502】と入力します。
④この方法は必ず守らなければならず、例えば単純桁で全ての断面、横桁間が明らかに上圧縮(5本),下引張(2本)である場合、[上リブ数=5][下リブ数=2]と一桁だけ入力してはいけません。
[上リブ数=502][下リブ数=502]と入力しておいて、プログラムが自動で上圧縮と判断して上リブ数入力の百の位【5】と下引張と判断して下リブ数入力の一の位の【2】を採用してきます。
⑤圧縮、引張側が明かな場合は面倒な入力ですが、目的は連続桁の交番区間で断面決定位置がどちらか不明な場合に便利な機能です。 |
| |
|
| Q18-7. |
左右腹板高異なる場合の腹板高
箱桁自動設計で左右の腹板高が違う時、そして平面曲線がある時に補剛材照査のl /bはどこの値を用いているのですか?
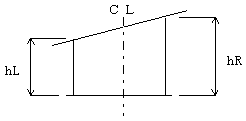 |
| A18-7. |
1.平面曲線がある時の間隔(a)は、左右の腹板上での長さを用いるのではなくて、桁長として管理しているライン上(箱板中心)での補剛材間隔を用います。
2.腹板高(b)は、左右の腹板のうち応力度の危険側の腹板を判断して、その腹板高を用いて照査します。(合成応力の大きい方の腹板を採用) |
| |
|
| Q18-8. |
合成I桁継手計算用応力度の決定
合成I桁自動設計で、継手計算用実応力度として乾燥収縮やクリープ、温度変化時の値を用いていますが、これらは考慮しなくてもよいのではないですか?
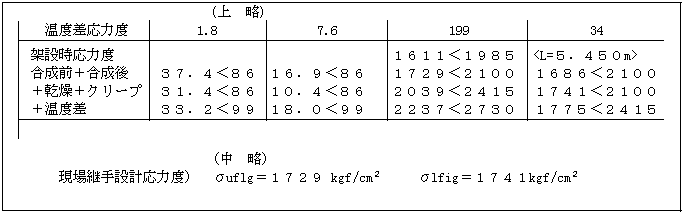 |
| A18-8. |
継手位置での断面計算を実行した時、上下フランジとも[合成前+後]、[+乾燥+クリープ]、[+温度]の3ケースを常時換算して最も危険な値を判断して、現場継手設計用応力度を採用しています。
このうち[+乾+クリープ]と[+温度]を無視したければ、入力によって選択が可能です。主桁設計の断面計算の為の初期設定の中で、[継手,補剛材の計算で二次応力無視]を[1]として、継手位置の断面計算を実行して下さい。

|
| |
|
| Q18-9. |
鉄道橋,歩道橋の機能
自動設計の主桁設計、断面計算の為の初期設定で
【鉄道橋=2】や【歩道橋=3】がありますが、何がちがうのですか? |
| A18-9. |
許容応力度が以下の様に変わります。
- 道路橋=1の時
- σa = σa (2100)
τa = τa (1200)
- 鉄道橋=2の時
- σa* = σa+100 (2100+100=2200)
τa = τa+ 50 (1200+50=1250)
(*但し、腹板下縁と下フランジのみ)
- 歩道橋=3の時
- σa = 1.15σa (1.15×2100=2415)
τa = 1.15τa (1.15×1200=1380)
鉄道橋は、非合成箱桁,鋼床版箱桁で利用できます。それ以外は全ての形式で利用できます。
尚、鉄道橋=4と歩道橋=5は将来のオプションとして表示しており、現在はどちらでも道路橋扱いとなります。
|
| |
|
| Q18-10. |
一覧表間隔照査,上段下段の意味
自動設計の主桁設計、断面計算で行われる垂直補剛材間隔の照査について、上段,下段の意味を教えて下さい。
また、着目した垂直補剛材で始終点側の間隔が異なる場合は、どちらで照査していますか? |
| A18-10. |
① 上段,下段という表現は曲げモーメント交番部において行われる、水平補剛材必要照査(DIN4114)
の為の表現で以下のとおりです。
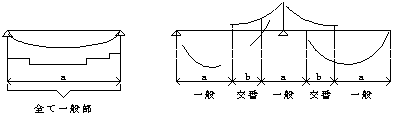
a)一般部での上段,下段は
上段 → Mmax時の応力度
下段 → Mmin時の応力度
を表示しています。つまり、
上段のσu
〃 σl
〃 τ
〃 σh
下段のσu
〃 σl
〃 τ |
→ Mmax時腹板上縁応力度
→ Mmax 〃 下縁 〃
→ Smax時の腹板せん断応力度
→Mmax時水平補剛材位置
→ Mmin時腹板上縁応力度
→ Mmin 〃 下縁 〃
→Smin時の腹板せん断応力度 |
です。この時あたりまえですが、Mmax時の照査しか必要ありませんので、判定式の道示の結果には、には、Mmax側(上段)にしか表示されません。下段は応力度を表示しているだけです。
b)交番部では、DIN4114に準拠した水平補剛材設置の判定(道示Ⅱ-8.4腹板 参照)を行う為に、
上段側 → 腹板上側に水平補剛材が必要か否かの照査を行っています。つまり、上側圧縮ですから応力度も一般部と同じ様に、Mmax時の結果となっています。
下段側 → 腹板下側に水平補剛材が必要か否かの照査を行っています。つまり、下側圧縮ですから応力度も一般部と同じ様に、Mmin時の結果となっています。
と分けており上や下段側のDINの項目に表示される値を見て、水平補剛材の必要を確認します。
尚、この時の垂直補剛材間隔の照査(道示)の値は、一般部の考えと全く同じ様に算出しています。結論から言うと、上段,下段はDIN4114の照査のための表示です。
② 垂直補剛材間隔が左右で異なる場合は、左右の大きい方で照査します。 |








