 Mighty
Bridge Q&A (1998/6/19) Mighty
Bridge Q&A (1998/6/19)
18.主桁設計
| Q18-5. |
垂直補剛材間隔照査
箱桁自動設計の垂直補剛材間隔照査で出力される一覧表の計算方法と、その見方について教えて下さい。 |
| A18-5. |
【垂直補剛材間隔照査】
出力表中,判別式の【道示】の数値は、道示Ⅱ-8.5に示される垂直補剛材間隔照査の計算結果です。計算に使用する圧縮応力度と、せん断応力度は、「主桁設計」の「断面計算の初期設定」の中に、組み合わせを指定する選択があります。
[補剛材間隔を組み合せ照査=0]の時、
応力度の組み合わせを以下の2ケースとし、大きい方のみを結果として印字する。
→ ケース1: 腹板圧縮縁応力度σ と 腹板圧縮縁せん断応力度τ
→ ケース2: 応力度σ=0 と 最大せん断応力度 τmax
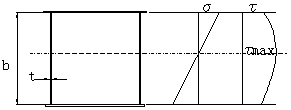
[補剛材間隔を組み合せ照査=0]の時、
腹板圧縮縁応力度σと、最大せん断応力度τmaxの組合わせでのみ照査します。
[図-1]

※ 次ページ以降に、上図-1の例で出力した結果と、例1~4の箇所について解説します。
【補剛材の照査】
(1) 垂直補剛材の照査は『道路橋示方書』8.5.1章に基づき照査を行なっている。
σu腹板上縁σlは下縁のσhは水平補剛材取付位置の応力度を示す。(圧縮は負)
但し応力状態が特殊な[D]の位置は『DIN4114』を用いている。
(2) 圧縮応力が生じる箇所に水平補剛材が必要かの照査は『DIN4114』により行なっている。
この場合には判別式が 1.0以上の箇所には水平補剛材を設ける必要がある。
(3) 圧縮応力度が上下段共に同じ側の場合には大きい方だけを照査している。
またこの場合は一方にしか水平補剛材が取りつかない為『DIN4114』は照査していない。
(4) 垂直補剛材間隔は着目点の前後の広い方を用いている。
(5) 判別式に用いる応力度は『道路橋示方書』はσUかσlとτの組合せとσ=0とτmaxの組合せで判別式が大きくなる方を、『DIN4114』は腹板中央部はτmaxを用いている。

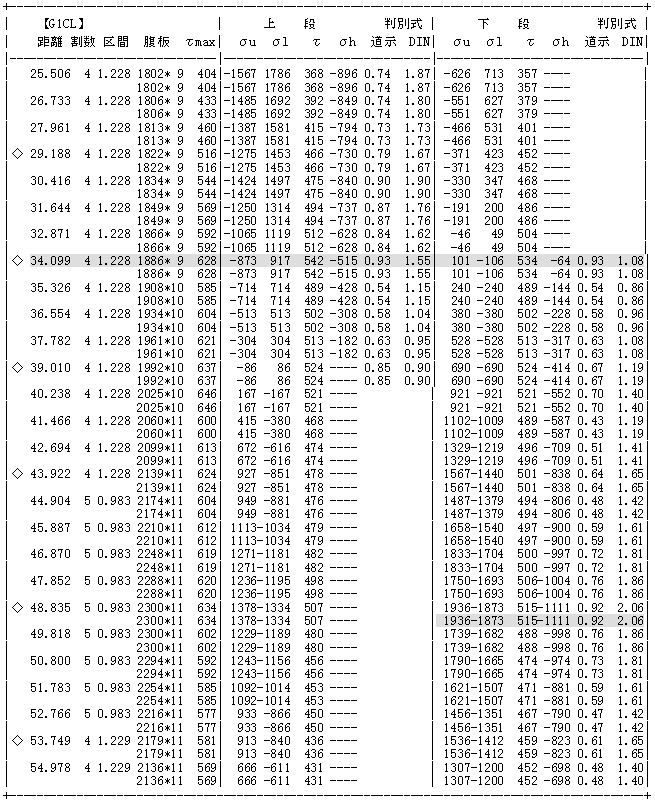
【例1:上側圧縮】
(計算用データ)
ウェブ圧縮縁 曲げ応力度 σ
ウェブ圧縮縁 せん断応力度 τ
最大 せん断応力度 τmax
ウェブ高 b
ウェブ厚 t
垂直補剛材間隔 a
水平補剛材段数 n |
= 1661kgf/c㎡
= 232kgf/c㎡
= 258kgf/c㎡
= 180.0cm
= 0.9cm
= 122.8cm
= 1段 |
 |
(計算結果) 寸法比 a/b= 122.8/ 180.0=
0.682
水平補剛材段数=1段 かつ a/b≦0.8 → 道示(解8.5.4)を適用する。
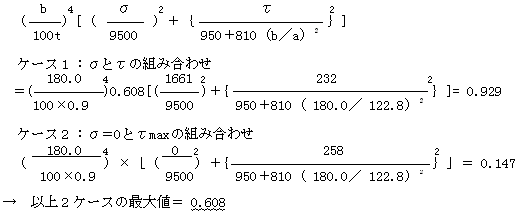
【例2:交番部で上側圧縮時】
(計算用データ)
ウェブ圧縮縁 曲げ応力度 σ
ウェブ圧縮縁 せん断応力度 τ
最大 せん断応力度 τmax
ウェブ高 b
ウェブ厚 t
垂直補剛材間隔 a
水平補剛材段数 n |
= 873kgf/c㎡
= 542kgf/c㎡
= 628kgf/c㎡
= 188.6cm
= 0.9cm
= 122.8cm
=1段 |
 |
(計算結果)
寸法比 a/b= 122.8/ 188.6= 0.651
水平補剛材段数=1段 かつ a/b≦0.8 → 道示(解8.5.4)を適用する。

→ 以上2ケースの最大値= 0.929
【例3:交番部で下側圧縮時】
(計算用データ)
ウェブ圧縮縁 曲げ応力度 σ
ウェブ圧縮縁 せん断応力度 τ
最大 せん断応力度 τmax
ウェブ高 b
ウェブ厚 t
垂直補剛材間隔 a
水平補剛材段数 n |
= 106kgf/c㎡
= 534kgf/c㎡
= 628kgf/c㎡
= 188.6cm
= 0.9cm
= 122.8cm
=1段 |
 |
(計算結果)
寸法比 a/b= 122.8/ 188.6= 0.651
水平補剛材段数=1段 かつ a/b≦0.8 → 道示(解8.5.4)を適用する。

【例4:下側圧縮時】
(計算用データ)
ウェブ圧縮縁 曲げ応力度 σ
ウェブ圧縮縁 せん断応力度 τ
最大 せん断応力度 τmax
ウェブ高 b
ウェブ厚 t
垂直補剛材間隔 a
水平補剛材段数 n |
= 1873kgf/c㎡
= 515kgf/c㎡
= 634kgf/c㎡
= 230.0cm
= 1.1cm
= 98.3cm
= 1段 |
 |
(計算結果)
寸法比 a/b= 98.3/ 230.0= 0.427
水平補剛材段数=1段 かつ a/b≦0.8 → 道示(解8.5.4)を適用する。
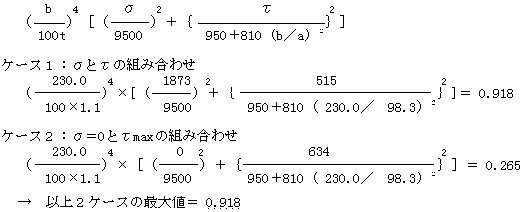
【DIN4114による水平補剛材必要チェック】
出力表中、判別式の[DIN]の数値は、道示Ⅱ-8.4の式(解8.4.5)を使用して、水平補剛材の必要チェックを行います。
座屈係数についてはデザインデータブックの座屈係数の欄を参照します。
本計算を行う場合、曲げモーメント交番部とそれ以外の箇所では計算に用いる応力度が異なります。以下に、2径間連続箱桁における適用例および計算例を記載します。
<2径間連続箱桁の例>
[図-1]
通常部:区間1,区間3,区間5
→照査区間: 腹板圧縮縁~腹板引張縁(下図では腹板高b)
応力度 : 腹板圧縮縁応力度σU,腹板引張縁応力度σL
,最大せん断応力度τmax
[図-2]
交番部:区間2,区間4
→ 照査区間: 腹板圧縮縁~引張側水平補剛材位置(下図ではbh)
応力度 : 腹板圧縮縁応力度σU,引張側水平補剛材位置の応力度σh,最大せん断応力度τmax
[図-3]
※ 次ページ以降に、出力結果抜粋,図-1の例1~4での計算例を記載します。
尚、荷重状態と座屈係数を下表に示します。(デザインデータブックより。)
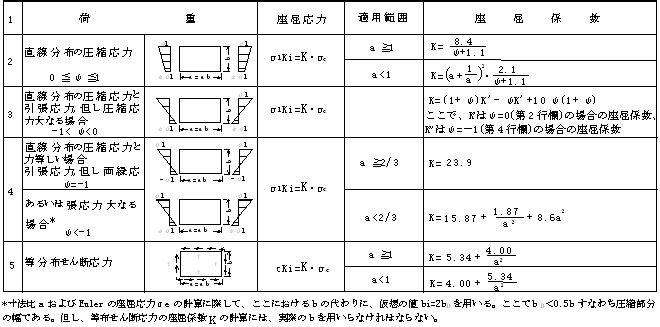
【補剛材の照査】
(1) 垂直補剛材の照査は『道路橋示方書』8.5.1章に基づき照査を行なっている。
σu腹板上縁σlは下縁のσhは水平補剛材取付位置の応力度を示す。(圧縮は負)
但し応力状態が特殊な[D]の位置は『DIN4114』を用いている。
(2) 圧縮応力が生じる箇所に水平補剛材が必要かの照査は『DIN4114』により行なっている。
この場合には判別式が 1.0以上の箇所には水平補剛材を設ける必要がある。
(3) 圧縮応力度が上下段共に同じ側の場合には大きい方だけを照査している。
またこの場合は一方にしか水平補剛材が取りつかない為『DIN4114』は照査していない。
(4) 垂直補剛材間隔は着目点の前後の広い方を用いている。
(5) 判別式に用いる応力度は『道路橋示方書』はσUかσlとτの組合せとσ=0とτmaxの組合せで判別式が大きくなる方を、『DIN4114』は腹板中央部はτmaxを用いている。

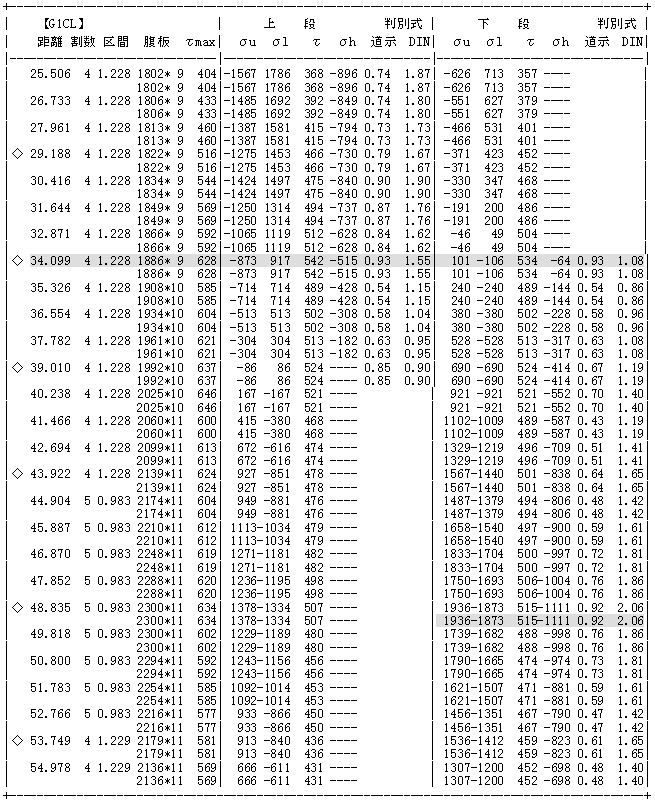
【例1:上側圧縮で交番部以外】
(計算用データ)
ウェブ圧縮縁 曲げ応力度 σU
ウェブ引張縁 曲げ応力度 σL
最大 せん断応力度 τmax
ウェブ高 b
ウェブ厚 tw
区間長 a
|
= 1661kgf/c㎡
= -1894kgf/c㎡
= 258kgf/c㎡
= 180.0cm
= 0.9cm
= 122.8cm |
 |
種別=交番区間でない
→ 交番区間でないので、
照査区間は腹板圧縮縁~引張縁 (=腹板高
b)
応力度は腹板の圧縮縁,引張縁の応力度(=σU,σL)を用いる。
(計算結果)
①座屈係数を求める(デザインデータブックの座屈係数より算出する)

②座屈パラメータ(道示.解8.4.3)
R=0.90-0.10φ=0.90-0.10×(-1.14028)=
1.01403
③座屈安全率(道示.解8.4.1)
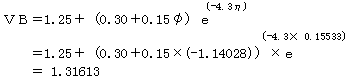
④(道示.解8.4.5)を解く。
左辺の値に対して右辺の値が大きくなれば、少なくとも1段以上の水平補剛材が必要という判定結果となる。


【例2:上側圧縮で交番部】
(計算用データ)
ウェブ圧縮縁 曲げ応力度 σU
ウェブ引張縁 曲げ応力度 σL
最大 せん断応力度 τmax
ウェブ高 b
ウェブ厚 tw
区間長 a
|
= 873kgf/c㎡
= -917kgf/c㎡
= 628kgf/c㎡
= 188.6cm
= 0.9cm
= 122.8cm |
 |
種別=交番区間である
→ 交番区間であるので、照査区間は圧縮縁~引張側水平補剛材位置(=bh)
応力度は腹板の圧縮縁,引張側水平補剛材位置の応力度(=σU,σh)を用いる。
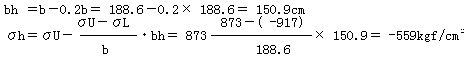
(計算結果) ①座屈係数を求める(デザインデータブックの座屈係数より算出する)

垂直応力度に対する座屈係数
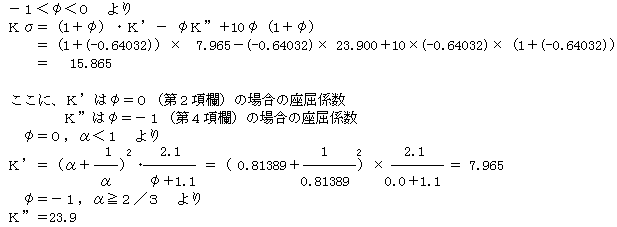
せん断応力度に対する座屈係数
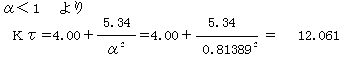
②座屈パラメータ(道示.解8.4.3)
R=0.90-0.10φ=0.90-0.10×(-0.64032)=
0.96403
③座屈安全率(道示.解8.4.1)

④(道示.解8.4.5)を解く。
左辺の値に対して右辺の値が大きくなれば、少なくとも1段以上の水平補剛材が必要という判定結果となる。

【例3:下側圧縮で交番部】
(計算用データ)
ウェブ圧縮縁 曲げ応力度 σU
ウェブ引張縁 曲げ応力度 σL
最大 せん断応力度 τmax
ウェブ高 b
ウェブ厚 tw
区間長 a
|
= 106kgf/c㎡
= -101kgf/c㎡
= 628kgf/c㎡
= 188.6cm
= 0.9cm
= 122.8cm |
 |
種別=交番区間である
→ 交番区間であるので、
照査区間は圧縮縁~引張側水平補剛材位置 (=bh)
応力度は腹板の圧縮縁,引張側水平補剛材位置の応力度(=σU,σh)を用いる。

(計算結果)
①座屈係数を求める(デザインデータブックの座屈係数より算出する)

④(道示.解8.4.5)を解く。
左辺の値に対して右辺の値が大きくなれば、少なくとも1段以上の水平補剛材が必要という判定結果となる。

【例4:下側圧縮で交番部以外】
(計算用データ)
ウェブ圧縮縁 曲げ応力度 σU
ウェブ引張縁 曲げ応力度 σL
最大 せん断応力度 τmax
ウェブ高 b
ウェブ厚 tw
区間長 a
|
= 1873kgf/c㎡
= -1936kgf/c㎡
= 634kgf/c㎡
= 230.0cm
= 1.1cm
= 98.3cm |
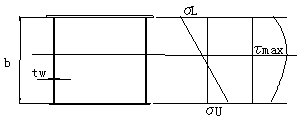 |
種別=交番区間でない
→ 交番区間でないので、
照査区間は腹板圧縮縁~引張縁 (=腹板高
b)
応力度は腹板の圧縮縁,引張縁の応力度(=σU,σL)を用いる。
(計算結果)
①座屈係数を求める(デザインデータブックの座屈係数より算出する)

②座屈パラメータ(道示.解8.4.3)
R=0.90-0.10φ=0.90-0.10×(-1.03364)=
1.00336
③座屈安全率(道示.解8.4.1)

④(道示.解8.4.5)を解く。左辺の値に対して右辺の値が大きくなれば、少なくとも1段以上の水平補剛材が必要という判定結果となる。


|
|







>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス
>> ファイナンシャルサポート
|








