| Q18-11. |
多室時腹板毎の腹板厚入力
箱桁自動設計で多室桁の設計を行った時、主桁設計の断面毎に設定するデータの中で[左腹板厚×100+右腹板厚]というメニューがありますが、これは何を入力するのですか?
また、通常入力する[腹板厚+材質]との関係を教えて下さい。
|
| A18-11. |
多室箱桁の設計で左右縁の腹板と、箱内の腹板の厚さを別々に入力できます。
これを利用するには、
1)断面計算の初期設定で[腹板毎に厚さを変える=1]
2)腹板厚+材質で箱内の腹板と材質を入力する。
3)左腹板厚×100+右腹板厚で左右縁の腹板厚を入力
する。
とします。
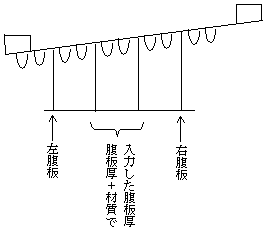 |
| |
|
| Q18-12 |
断面計算時の内部リブ配置方法
鋼床版の張出部にリブ本数を入力すると、内部ではどの様に配置して断面計算を行っているのでしょうか? |
| A18-12. |
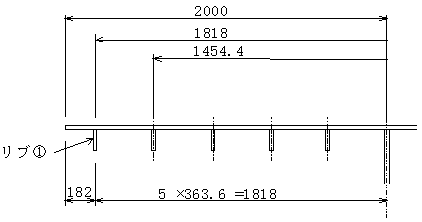
[条件]
1.合成前張出部を例とする
2.張出部 L=2000㎜
3.リブ本数 n=5本
[リブ配置]
マニュアルより腹板中心から張出先端へ向ってのリブ間隔は、
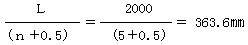
となり上図のように配置されます。(先端の残り182mm)
この状態に計算された有効幅があてはめられ指定するリブオプションのスイッチにより有効幅境に位置するリブが有効か否かの判定を下図のように行います。
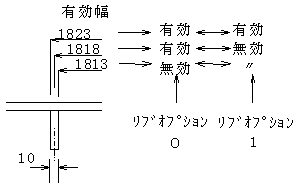 |
| |
|
| Q18-13. |
合成I桁断面の抵抗モーメントの算出
抵抗モーメントはどの様にして算出しているのですか? |
| A18-13. |
上下フランジとも合計モーメントの値に応力度の比を各ケース毎に乗じて、最も危険となるケースでの結果を使用して抵抗モーメントとしています。正しくはモーメントの余り量とも言えます。
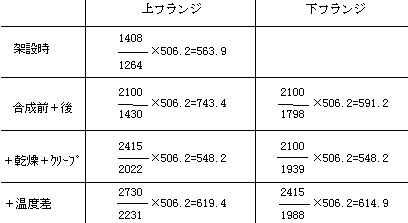
 |
| |
|
| Q18-14. |
合成箱桁せん断応力度の算出
合成箱桁断面計算で、合成後のせん断応力度の算出方法について例をもとに、解説して下さい。 |
| A18-14. |
1.合成前:曲げによるせん断応力度(Ss)
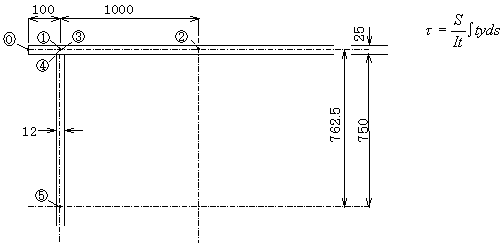
[線積分]

[せん断応力度]
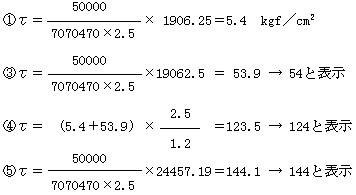
2.合成前:ねじりモーメントによるせん断応力度(MTS)

3.合成後:曲げによるせん断応力度(Sv)

[線積分]

[せん断応力度]
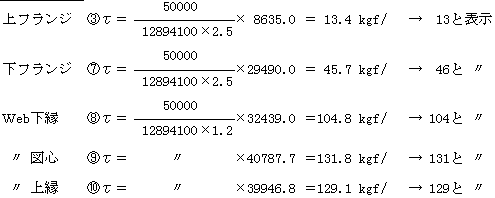
4.合成後:ねじりモーメントによるせん断応力度(MTv)

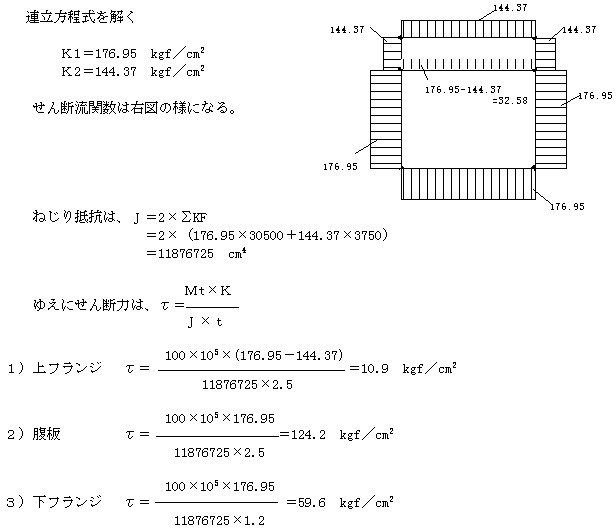

|
| |
|
| Q18-15. |
継手、補剛材計算で2次応力無視=1
「合成I桁自動設計」、「断面計算の初期設定」の入力項目の一番下に「継手補剛材の計算で2次応力無視=1」とありますが、これはどの様な働きをするのでしょうか? |
| A18-15. |
現場継手位置での断面計算を実行して得られる実応力度を、現場継手ボルト本数計算用として採用する際、応力度の組み合わせのうちどのケースを採用するかを指示します。
【0】の時:常時、常時+乾燥+クリープ、+温度変化の3ケースを常時換算して、最大となる値を採用。上下フランジで荷重ケースが異なる場合もある。
【1】の時:2次応力でのケースを無視し、常時での実応力度をそのまま採用する。


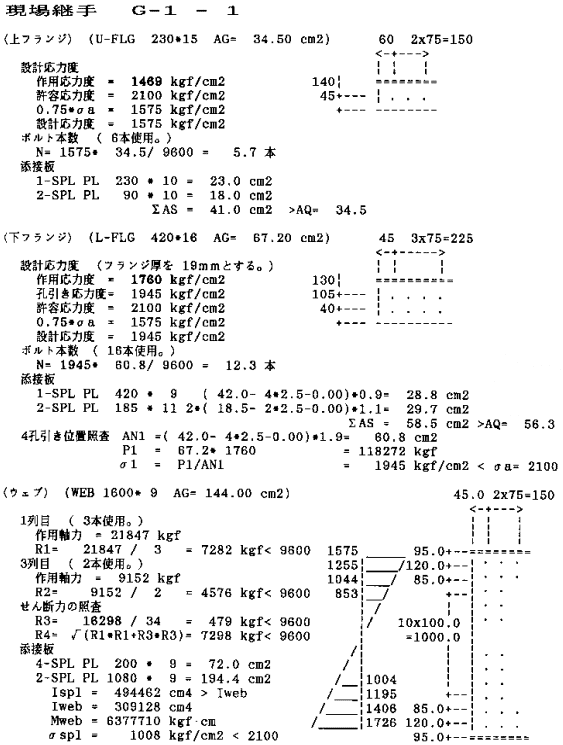

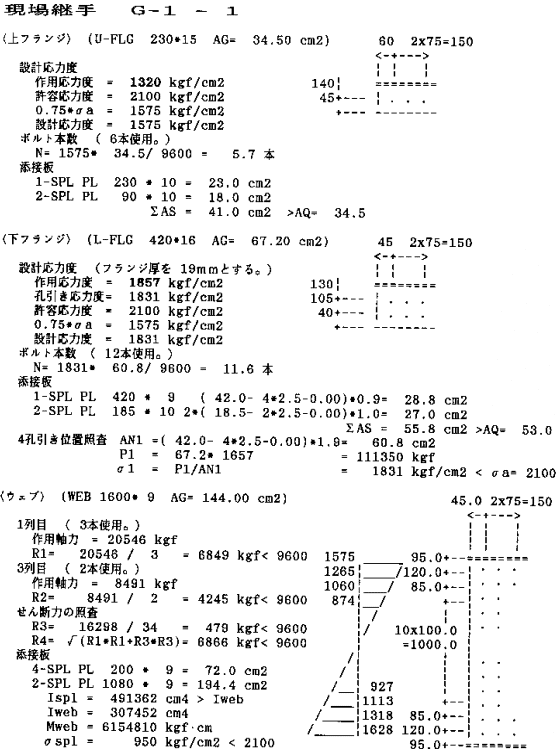
|
| |
|
| Q18-16. |
モーメントプレートなしの入力
モーメントプレートなしとし、シアプレートのみにしたいのですが、どの様に入力すればよいのでしょうか? |
| A18-16. |
①「配列の初期設定」画面で、【モーメントプレート厚=0】として下さい。
②この時、入力項目のうち「モーメントプレートのボルト本数」に入力する値がシアプレートのボルト本数としても利用されますので、【0】とせずシアプレートのボルト本数を入力して下さい。 |
| |
|
| Q18-17. |
I桁引張フランジ孔引き照査
引張フランジのボルトを千鳥配置とした時、母材及び添接板の純断面積の算出方法を教えて下さい。 |
| A18-17. |
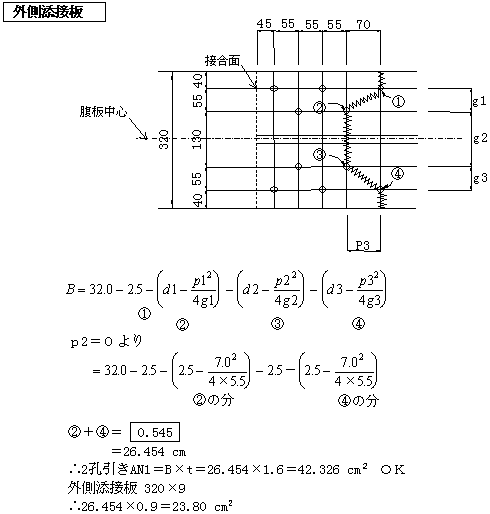
 |
| |
|
| Q18-18. |
箱桁初期設定で添接面積を千鳥で計算=1
配列の初期設定で「添接面積を千鳥で計算=1」という項目がありますが、どの様なときに使い分けるのか教えて下さい。 |
| A18-18. |
千鳥の時の引張添接板、必要断面計算において
0の時 → As = 2枚の添接板純断面積合計
AQ = 第1列目のフランジ母材純断面積
As > AQとして比較します
1の時 → As = 2列目(全孔)での添接板純断面積合計
[As]= 1列目(千鳥) 〃
〃
AQ = 2列目(全孔)でのフランジ母材純断面積
[AQ]= 1列目(千鳥) 〃
〃
∴ As > AQ とそれぞれ比較します。この方法は特に基準等はなく、ひとつの機能として設けているだけです。
フランジ母材に10tonfが作用した時の例
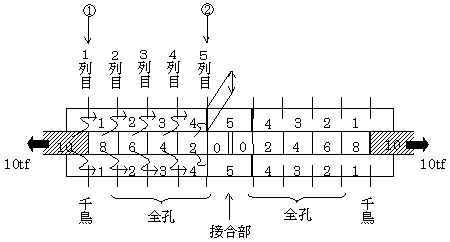
- step1
- 母材にとっては、1列目(千鳥)で10tonfを受けるのでここで母材の孔引き照査が決まる。1列目のボルトよりフランジに力が流れ、上下に1tonfずつ流れるので1列目と2列目の間ででは
フランジ母材 =10-1×2=8ton
添接板 =各 1ton
が流れている。
- step2
- 2列目のボルトで更に、1tonfが流れ2~3列目の区間では
フランジ母材 =8-1×2=6tonf
添接板 =各 2tonf が
流れる。
- step3
- この様にして行くと5列目では全てフランジ添接板に流れてしまい母材は0となることから、添接板に作用する力はここが(全孔)最大になる。
- step4
- ゆえに、1列目(千鳥)の母材純断面積AQ<5列目(全孔)の添接板純断面積Asを比較する方法が通常で、上記の指定は【0】の場合です。
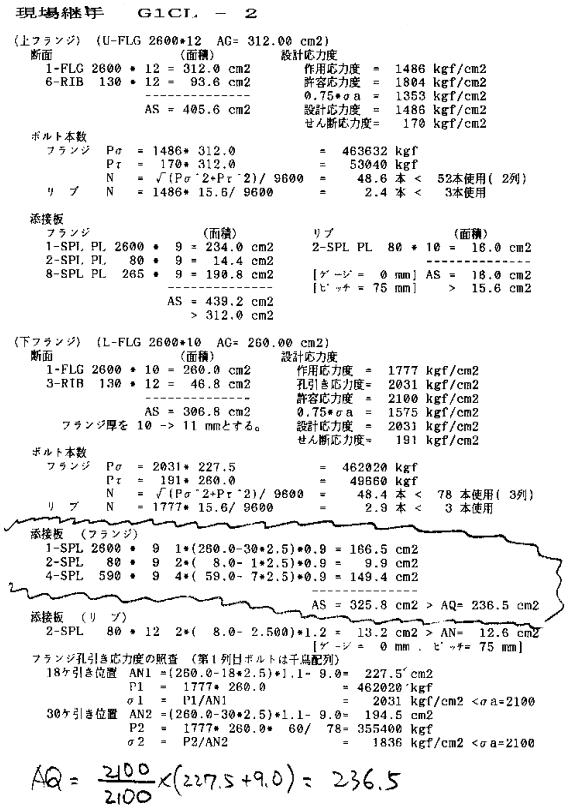

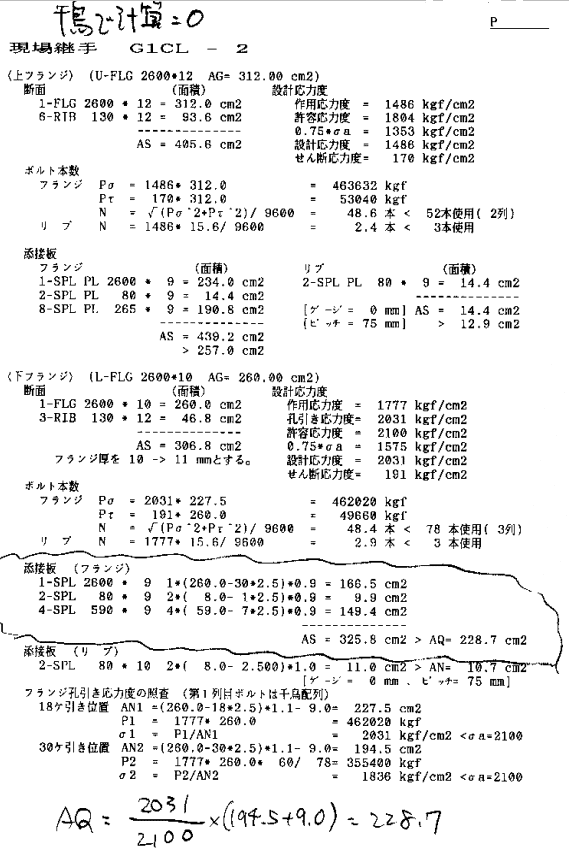
|








